洋楽名盤紹介と日々の雑談を書いてます
第17回名盤シリーズ
今回はクラシック作品のロック化「展覧会の絵」。
(1971年作品)
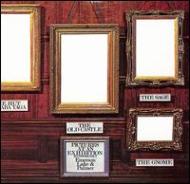
エマーソン・レイク&パーマー(略してELP)の作品で1stから「恐怖の頭脳改革」までのアルバムはどれも名作で聴き応え満点なのだが、クラシックからの大々的な引用など話題性が高かった本作品を紹介しよう。
知っての通り、この曲の原曲はムゾルグスキーのピアノ組曲「展覧会の絵」であり、それのロック・バージョンである。
このELPバージョンは管弦楽用にラヴェルが編曲したバージョンを手本にしている。
ただし、そっくりそのままコピーするのではなく、組曲の中からの抜粋であり、またオリジナル曲を編入したり、新たに歌詞を加えたりしている。
私はまず、この曲を題材に選んだセンスがすごいと思う。
バッハでもモーツァルトでもなく、かと言って誰も知らない曲でもない。
知ってる人は多いが、有名すぎない微妙なところで選んだのだろう。
このアルバムはライブ録音で、当初はライブ専用曲でレコーディングの予定は無かったと言われている。
レコーディングを行って発売されるまでの経緯に、グレッグ・レイクとキース・エマーソンの対立があったと言われているが、レイクは発売を熱望しエマーソンは拒否、しかしこれが大ヒットとなりレイクの思惑通りに事が進んだようだ。
パイプ・オルガンの音色でプロムナード、あの有名なメロディが奏でられる。
この組曲では3回プロムナードが登場するが、2回目はレイクの独唱、3回目はバンド演奏だ。
2回目のプロムナードのあとにはレイクのフォーク・ソング「THE SAGE」。
それほど違和感なく溶け込んでいるが、クラシックの原曲に歌を入れるのはいろいろと困難があるのが想像できる。
次の「THE OLD CASTLE」の前半部分にキースによるムーグシンセサイザーのデモ演奏のようなパートがあるのだが、さすがにこれは時代を感じてしまう部分かもしれない。
しかし当時としてはシンセサイザー自体が珍しい状況だったので、こういうのも「あり」だったのだろう。
中盤のバンド演奏によるプロムナードから先は、どんどんエキサイトした演奏が繰り広げられていく。
「バーバヤーガの小屋」はほぼ原曲のまま、しかし非常ハードに演奏され、次のオリジナル曲「バーバヤーガの呪い」につながっていく。
レイクのワウを使ったベースがクリムゾン出身であることを感じさせるが、この演奏は完全にハード・ロックだ。
中でもパーマーの手数の多いドラムがカッコイイ。
再び「バーバヤーガの小屋」のフレーズが繰り返され、ラストの威風堂々とした「キエフの大門」へ。
原曲にオリジナルの歌詞をつけたこの曲のラストは、キースによるオルガンとの格闘シーンへ。
オルガンを蹴飛ばし、ひっくり返し、ナイフを突き立てる…。
ジミヘンのオルガンバージョンのようなパフォーマンスを繰り広げ、客を沸かせて終了。
私はELPよりも、カラヤン指揮ベルリン・フィル・ハーモニー楽団のラベル編曲「展覧会の絵」を先に聴いた。
このライブ演奏、確かに現代の耳で聴くと、時代を感じさせる部分はなくはないが、70年代初頭としては相当新鮮な音楽だっただろう。
最後にもう1曲「NUTROCKER(くるみ割り人形)」のELPバージョンも入っている。
私の持っているCDだと「展覧会の絵」の93年リメイクバージョンも入っていて、なかなか円熟味のある演奏が聴けてけっこう好きなのだが、全盛期を知る人からすると評判悪いようだ。
今回はクラシック作品のロック化「展覧会の絵」。
(1971年作品)
エマーソン・レイク&パーマー(略してELP)の作品で1stから「恐怖の頭脳改革」までのアルバムはどれも名作で聴き応え満点なのだが、クラシックからの大々的な引用など話題性が高かった本作品を紹介しよう。
知っての通り、この曲の原曲はムゾルグスキーのピアノ組曲「展覧会の絵」であり、それのロック・バージョンである。
このELPバージョンは管弦楽用にラヴェルが編曲したバージョンを手本にしている。
ただし、そっくりそのままコピーするのではなく、組曲の中からの抜粋であり、またオリジナル曲を編入したり、新たに歌詞を加えたりしている。
私はまず、この曲を題材に選んだセンスがすごいと思う。
バッハでもモーツァルトでもなく、かと言って誰も知らない曲でもない。
知ってる人は多いが、有名すぎない微妙なところで選んだのだろう。
このアルバムはライブ録音で、当初はライブ専用曲でレコーディングの予定は無かったと言われている。
レコーディングを行って発売されるまでの経緯に、グレッグ・レイクとキース・エマーソンの対立があったと言われているが、レイクは発売を熱望しエマーソンは拒否、しかしこれが大ヒットとなりレイクの思惑通りに事が進んだようだ。
パイプ・オルガンの音色でプロムナード、あの有名なメロディが奏でられる。
この組曲では3回プロムナードが登場するが、2回目はレイクの独唱、3回目はバンド演奏だ。
2回目のプロムナードのあとにはレイクのフォーク・ソング「THE SAGE」。
それほど違和感なく溶け込んでいるが、クラシックの原曲に歌を入れるのはいろいろと困難があるのが想像できる。
次の「THE OLD CASTLE」の前半部分にキースによるムーグシンセサイザーのデモ演奏のようなパートがあるのだが、さすがにこれは時代を感じてしまう部分かもしれない。
しかし当時としてはシンセサイザー自体が珍しい状況だったので、こういうのも「あり」だったのだろう。
中盤のバンド演奏によるプロムナードから先は、どんどんエキサイトした演奏が繰り広げられていく。
「バーバヤーガの小屋」はほぼ原曲のまま、しかし非常ハードに演奏され、次のオリジナル曲「バーバヤーガの呪い」につながっていく。
レイクのワウを使ったベースがクリムゾン出身であることを感じさせるが、この演奏は完全にハード・ロックだ。
中でもパーマーの手数の多いドラムがカッコイイ。
再び「バーバヤーガの小屋」のフレーズが繰り返され、ラストの威風堂々とした「キエフの大門」へ。
原曲にオリジナルの歌詞をつけたこの曲のラストは、キースによるオルガンとの格闘シーンへ。
オルガンを蹴飛ばし、ひっくり返し、ナイフを突き立てる…。
ジミヘンのオルガンバージョンのようなパフォーマンスを繰り広げ、客を沸かせて終了。
私はELPよりも、カラヤン指揮ベルリン・フィル・ハーモニー楽団のラベル編曲「展覧会の絵」を先に聴いた。
このライブ演奏、確かに現代の耳で聴くと、時代を感じさせる部分はなくはないが、70年代初頭としては相当新鮮な音楽だっただろう。
最後にもう1曲「NUTROCKER(くるみ割り人形)」のELPバージョンも入っている。
私の持っているCDだと「展覧会の絵」の93年リメイクバージョンも入っていて、なかなか円熟味のある演奏が聴けてけっこう好きなのだが、全盛期を知る人からすると評判悪いようだ。
| 名盤100選へ戻る |
PR
第16回名盤シリーズ
ジェファーソン・エアプレインの初期のアルバム「シュール・リアリスティック・ピロー」
(1967年作品)
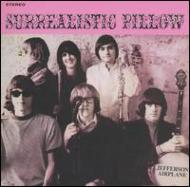
ジェファーソン・エアプレーンは、当時グレイトフル・デッドやクイック・シルバー・メッセンジャー・サービスらと共に「シスコ・ロック」と呼ばれ、アメリカのサイケシーンを引っ張っていた。
中でもジェファーソン・エアプレーンはその代表的な存在として、ブリティッシュロック勢に対抗する新時代のアメリカン・バンドだった。
67年発表の「シュール・リアリスティック・ピロー」は彼らのセカンド・アルバムで、当時アメリカで大ヒットを飛ばし一躍大物バンドの仲間入りを果たしたのだった。
私がこのバンドを知ったのは「ギミー・シェルター」という映画だ。
オルタモントの悲劇で知られるローリング・ストーンズ主催のフリー・コンサートのドキュメントだが、今にも暴動がおこりそうな大観衆の中で一生懸命演奏し歌う姿が印象的だった。
メンバーはマーティ・ベイリン(vo)、ポール・カントナー(g、vo)、ヨーマ・コーコネン(g)、スペンサード・ライデン(ds)、ジャック・キャサディ(b)、そしてこのアルバムから加入した紅一点のグレイス・スリック(vo)だ。
このアルバムからのシングル曲である「Somebody to Love」「White Rabbit」は大ヒットを飛ばすのだが、これは新加入のグレイスの以前からの持ち歌だったようだ。
いちおうサイケ・バンドとしてカテゴリーされる彼らだが、このアルバムを聴くとそれほどサイケな感じはしない。
とくにサウンド面では、フォークを基本としたオーソドックスな感じがする。
しかし、歌詞の内容や題名には彼らならではの謎な部分があるのも事実。
例えば1曲目は「She has funny cars(おかしな車)」という題名だが、歌詞のどこにも車の話題がない。
6曲目「3/5 of a Mile in 10seconds」、7曲目「D.C.B.A.-25」などは、まるで意味不明だ。
大ヒット曲の「White Rabbit」はドラッグ・ソングで、60年代後半という時代を反映している。
この曲はベトナム戦争の映画「プラトーン」にも使われたようだ。
淡々とした曲だが、序所に盛り上がっていき、魅力たっぷりの燐とした力強いボーカルが実にカッコイイ。
アルバムの半ばあたりに、フォーク調の大人しめの曲が並んでいるが、このバンドのルーツにはフォークがあるのだろう。
なかでも7曲目「D.C.B.A.-25」、8曲目「素敵なあの娘」は綺麗なハーモニーと美しいメロディがあり、このアルバムを華やかに演出している。
対して1曲目「おかしな車」、2曲目「Somebody to Love」、6曲目「恋して行こう」、11曲目「PLASTICK FANTERJIK LOVER」は力強い曲。
グレイスの力強いボーカルが印象的だ。
ジェファーソン・エアプレインにはその後、ジェファーソン・スターシップ、ホット・ツナ、スターシップと名前を変えて進化していくのだが、まだ未聴だ。
ジェファーソン・エアプレインの初期のアルバム「シュール・リアリスティック・ピロー」
(1967年作品)
ジェファーソン・エアプレーンは、当時グレイトフル・デッドやクイック・シルバー・メッセンジャー・サービスらと共に「シスコ・ロック」と呼ばれ、アメリカのサイケシーンを引っ張っていた。
中でもジェファーソン・エアプレーンはその代表的な存在として、ブリティッシュロック勢に対抗する新時代のアメリカン・バンドだった。
67年発表の「シュール・リアリスティック・ピロー」は彼らのセカンド・アルバムで、当時アメリカで大ヒットを飛ばし一躍大物バンドの仲間入りを果たしたのだった。
私がこのバンドを知ったのは「ギミー・シェルター」という映画だ。
オルタモントの悲劇で知られるローリング・ストーンズ主催のフリー・コンサートのドキュメントだが、今にも暴動がおこりそうな大観衆の中で一生懸命演奏し歌う姿が印象的だった。
メンバーはマーティ・ベイリン(vo)、ポール・カントナー(g、vo)、ヨーマ・コーコネン(g)、スペンサード・ライデン(ds)、ジャック・キャサディ(b)、そしてこのアルバムから加入した紅一点のグレイス・スリック(vo)だ。
このアルバムからのシングル曲である「Somebody to Love」「White Rabbit」は大ヒットを飛ばすのだが、これは新加入のグレイスの以前からの持ち歌だったようだ。
いちおうサイケ・バンドとしてカテゴリーされる彼らだが、このアルバムを聴くとそれほどサイケな感じはしない。
とくにサウンド面では、フォークを基本としたオーソドックスな感じがする。
しかし、歌詞の内容や題名には彼らならではの謎な部分があるのも事実。
例えば1曲目は「She has funny cars(おかしな車)」という題名だが、歌詞のどこにも車の話題がない。
6曲目「3/5 of a Mile in 10seconds」、7曲目「D.C.B.A.-25」などは、まるで意味不明だ。
大ヒット曲の「White Rabbit」はドラッグ・ソングで、60年代後半という時代を反映している。
この曲はベトナム戦争の映画「プラトーン」にも使われたようだ。
淡々とした曲だが、序所に盛り上がっていき、魅力たっぷりの燐とした力強いボーカルが実にカッコイイ。
アルバムの半ばあたりに、フォーク調の大人しめの曲が並んでいるが、このバンドのルーツにはフォークがあるのだろう。
なかでも7曲目「D.C.B.A.-25」、8曲目「素敵なあの娘」は綺麗なハーモニーと美しいメロディがあり、このアルバムを華やかに演出している。
対して1曲目「おかしな車」、2曲目「Somebody to Love」、6曲目「恋して行こう」、11曲目「PLASTICK FANTERJIK LOVER」は力強い曲。
グレイスの力強いボーカルが印象的だ。
ジェファーソン・エアプレインにはその後、ジェファーソン・スターシップ、ホット・ツナ、スターシップと名前を変えて進化していくのだが、まだ未聴だ。
| 名盤100選へ戻る |
第15回名盤シリーズ
今回取り上げるのはジェフ・ベックの名インスト・アルバム「ブロウ・バイ・ブロウ」
(1975年作品)
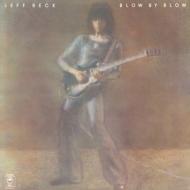
1975年発表のこのアルバムは、全曲インストゥルメンタルで、ロックというよりジャズ・ロックかフュージョンに近い。
それはジェフ・ベックのカラフルなギター・サウンドと相まってとてもファンキーな仕上がりとなっている。
このアルバム発表までのジェフは、ヤード・バーズ脱退後、ジェフ・ベック・グループ、ベック・ボガード&アピスなどの強力なバンドを経験し、ロッド・スチュアートやロン・ウッドなど大物ミュージシャンと競演してきた。
しかし、その気難しい性格から、バンド活動は不向きだったようで、ここからソロ活動をスタートする。
ちなみに、ミック・テイラー脱退後のローリング・ストーンズ参加の噂もあったようだが、入ったとしても長続きしていないだろう。
プロデューサーはジョージ・マーチン。
そう、ビートルズのプロデューサーとして有名なあの人だ。
そのせいか、ビートルズの「SHE'S A WOMAN」のレゲエ・バージョンが収録されている。
バック・メンバーにはマックス・ミドルトンなどの若手実力派ミュージシャンで、しっかりバックを支えている。
1曲目「YOU KNOW WHAT I MEAN」からファンキーな曲がスタート。
第2期ジェフ・ベック・グループ時代、すでにファンキー路線を模索していたが、ここにきて完成形に至ったように思う。
4曲目「AIR BLOWER」、7曲目「THELONIUS」あたりのファンク曲もそうだが、マックス・ミドルトンのキーボードプレイが実にいい仕事をしている。
また、収録曲全てにいえることだが、ドラムが手数が多く、カコイイのもこのアルバムの特徴だ。
ここでのジェフのプレイだが、例えば一つのギターソロ内で何度もピックアップを切り替えたり、ピッキングのアタックを変えたりなど、そのサウンドに表情をつけ、その表現力の幅の広さに驚く。
それがもっとも顕著に現れているのがスティービー・ワンダー作曲「悲しみの恋人達」だろう。
ギターが歌っている。
下手なボーカリストよりもずっと歌っているのである。
例えば、前半と後半でテーマ部のメロデイが繰り返されるのだが、一見同じメロディに聴こえて、実は毎回少しづつ表情を変えている。
とくに後半に出てくるパターンは泣けてくるほど、味のあるプレイだ。
そして中間部のソロプレイ、何度聴いても味わい深く、1音たりともムダな音がない。
まさに名演中の名演だ。
このアルバムでもっともスリリングなのが5曲目「SCATTERBRAIN」。
変拍子のリズムに乗った一度聴いたら忘れられないリフ、実際のスピードはそれほどでもないのに、スピード感あふれるギターソロ、それらを、必死で弾いてるのではなく、気楽に伸び伸びと弾いているようでさすがだといわざるを得ない。
今回取り上げるのはジェフ・ベックの名インスト・アルバム「ブロウ・バイ・ブロウ」
(1975年作品)
1975年発表のこのアルバムは、全曲インストゥルメンタルで、ロックというよりジャズ・ロックかフュージョンに近い。
それはジェフ・ベックのカラフルなギター・サウンドと相まってとてもファンキーな仕上がりとなっている。
このアルバム発表までのジェフは、ヤード・バーズ脱退後、ジェフ・ベック・グループ、ベック・ボガード&アピスなどの強力なバンドを経験し、ロッド・スチュアートやロン・ウッドなど大物ミュージシャンと競演してきた。
しかし、その気難しい性格から、バンド活動は不向きだったようで、ここからソロ活動をスタートする。
ちなみに、ミック・テイラー脱退後のローリング・ストーンズ参加の噂もあったようだが、入ったとしても長続きしていないだろう。
プロデューサーはジョージ・マーチン。
そう、ビートルズのプロデューサーとして有名なあの人だ。
そのせいか、ビートルズの「SHE'S A WOMAN」のレゲエ・バージョンが収録されている。
バック・メンバーにはマックス・ミドルトンなどの若手実力派ミュージシャンで、しっかりバックを支えている。
1曲目「YOU KNOW WHAT I MEAN」からファンキーな曲がスタート。
第2期ジェフ・ベック・グループ時代、すでにファンキー路線を模索していたが、ここにきて完成形に至ったように思う。
4曲目「AIR BLOWER」、7曲目「THELONIUS」あたりのファンク曲もそうだが、マックス・ミドルトンのキーボードプレイが実にいい仕事をしている。
また、収録曲全てにいえることだが、ドラムが手数が多く、カコイイのもこのアルバムの特徴だ。
ここでのジェフのプレイだが、例えば一つのギターソロ内で何度もピックアップを切り替えたり、ピッキングのアタックを変えたりなど、そのサウンドに表情をつけ、その表現力の幅の広さに驚く。
それがもっとも顕著に現れているのがスティービー・ワンダー作曲「悲しみの恋人達」だろう。
ギターが歌っている。
下手なボーカリストよりもずっと歌っているのである。
例えば、前半と後半でテーマ部のメロデイが繰り返されるのだが、一見同じメロディに聴こえて、実は毎回少しづつ表情を変えている。
とくに後半に出てくるパターンは泣けてくるほど、味のあるプレイだ。
そして中間部のソロプレイ、何度聴いても味わい深く、1音たりともムダな音がない。
まさに名演中の名演だ。
このアルバムでもっともスリリングなのが5曲目「SCATTERBRAIN」。
変拍子のリズムに乗った一度聴いたら忘れられないリフ、実際のスピードはそれほどでもないのに、スピード感あふれるギターソロ、それらを、必死で弾いてるのではなく、気楽に伸び伸びと弾いているようでさすがだといわざるを得ない。
| 名盤100選へ戻る |
第14回名盤シリーズ
ヘヴィ・メタルの原点、ブラック・サバス「黒い安息日」
(1970年作品)
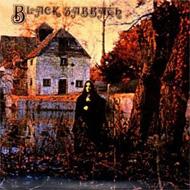
ブラック・サバスのファースト・アルバム。
メンバーはトニーアイオミ(g)、オジーオズボーン(vo)、ギーザーバトラー(b)、ビルワード(ds)の4人だ。
雨が降り雷が鳴り響く中、遠くで寂しげな鐘の音。
もうこの時点で、このアルバムが普通でないことがわかる。
そして、それらを引き裂くがごときリフが登場する。
重く、暗く、遅く、そしてホラーのように怖い。
私は今まで相当な数の曲を聴いているが、この曲ほど暗く重い曲を他に知らない。
オジーの狂人のようなボーカル、ビルのオバケが出てきそうなドラム、そしてアイオミの不気味なギターリフ。
実に斬新であり、今聴いても古さを感じさせないのはどうだ。
13日の金曜日に発売されたこのアルバム、これを当時の人はどう思ったのだろうか。
衝撃的なのは表題曲だけではない。
「N.I.B.」も不気味なベースソロから始まるが、これもヘヴィでサバスらしい曲だ。
しかし、この曲では悲壮感漂いながらも、かすかに美しさが見え隠れする。
とくにギターソロだ。
何本かのギターがオーバーダブされているが、ところどころ、ハッとするほど美しい瞬間がある。
珍しくオジーのブルーズハープが聴ける「THE WIZARD」もいい。
ヘヴィなギターリフのバックは、ビルの破壊的なドラムワーク。
この曲を聴くとサバスの演奏力の高さを窺い知ることが出来る。
とくにリズム隊の強力さは、同時代のレッド・ツェッペリンと比較しても遜色ないのではないだろうか?
あまり演奏面で語られることのないサバスだが、元々はジャズやブルースを得意とするバンドだっただけあり、相当なレベルにあると思う。
また、サバスのブルースサイドを垣間見ることができるのは「WARNING」。
シンプルな前半部分、ここでのアイオミのギターはとても歌心溢れるソロを展開しており、ブルージーでとても味わい深い。
この曲の後半部分から、ギターを中心としたインストパートへと発展していく。
元々はインプロから発展したものだと思われる部分だが、こういった曲をアルバムに収録するのはある種の実験みたいなものだと思う。
これもバンドの実力がないとグダグダになってしまい勝ちだが、最後までだれることなく上手くまとめている。
ご存知の方も多いと思うが、アイオミの右手は、中指と薬指が途中から事故で切断されてなくなっている。
彼は左利きなので、ギターのフレットを押さえる側の手に大きな欠陥を抱えるのだ。
サバス・サウンドの要となる、ヘヴィで不気味なリフ、流麗なギターソロは、この不自由な手でなければ出てこなかったと言われている。
ヘヴィ・メタルの原点、ブラック・サバス「黒い安息日」
(1970年作品)
ブラック・サバスのファースト・アルバム。
メンバーはトニーアイオミ(g)、オジーオズボーン(vo)、ギーザーバトラー(b)、ビルワード(ds)の4人だ。
雨が降り雷が鳴り響く中、遠くで寂しげな鐘の音。
もうこの時点で、このアルバムが普通でないことがわかる。
そして、それらを引き裂くがごときリフが登場する。
重く、暗く、遅く、そしてホラーのように怖い。
私は今まで相当な数の曲を聴いているが、この曲ほど暗く重い曲を他に知らない。
オジーの狂人のようなボーカル、ビルのオバケが出てきそうなドラム、そしてアイオミの不気味なギターリフ。
実に斬新であり、今聴いても古さを感じさせないのはどうだ。
13日の金曜日に発売されたこのアルバム、これを当時の人はどう思ったのだろうか。
衝撃的なのは表題曲だけではない。
「N.I.B.」も不気味なベースソロから始まるが、これもヘヴィでサバスらしい曲だ。
しかし、この曲では悲壮感漂いながらも、かすかに美しさが見え隠れする。
とくにギターソロだ。
何本かのギターがオーバーダブされているが、ところどころ、ハッとするほど美しい瞬間がある。
珍しくオジーのブルーズハープが聴ける「THE WIZARD」もいい。
ヘヴィなギターリフのバックは、ビルの破壊的なドラムワーク。
この曲を聴くとサバスの演奏力の高さを窺い知ることが出来る。
とくにリズム隊の強力さは、同時代のレッド・ツェッペリンと比較しても遜色ないのではないだろうか?
あまり演奏面で語られることのないサバスだが、元々はジャズやブルースを得意とするバンドだっただけあり、相当なレベルにあると思う。
また、サバスのブルースサイドを垣間見ることができるのは「WARNING」。
シンプルな前半部分、ここでのアイオミのギターはとても歌心溢れるソロを展開しており、ブルージーでとても味わい深い。
この曲の後半部分から、ギターを中心としたインストパートへと発展していく。
元々はインプロから発展したものだと思われる部分だが、こういった曲をアルバムに収録するのはある種の実験みたいなものだと思う。
これもバンドの実力がないとグダグダになってしまい勝ちだが、最後までだれることなく上手くまとめている。
ご存知の方も多いと思うが、アイオミの右手は、中指と薬指が途中から事故で切断されてなくなっている。
彼は左利きなので、ギターのフレットを押さえる側の手に大きな欠陥を抱えるのだ。
サバス・サウンドの要となる、ヘヴィで不気味なリフ、流麗なギターソロは、この不自由な手でなければ出てこなかったと言われている。
| 名盤100選へ戻る |
第13回名盤シリーズ
実質ジョン・レノンのソロ・ファースト・アルバムともいえる「ジョンの魂」
(1970年作品)
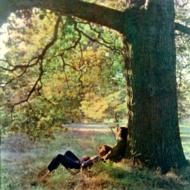
「なんて重苦しいアルバムなんだろう」
これがこのアルバムを聴いた初めの感想だった。
このアルバムを初めて聴いたのは15か16の頃。
その頃ビートルズの楽曲は全て聴いたので、次は各メンバーのソロを聴きたいと思ってたのだが、ちょうどラジオでエアチェックした「Love」をとても気にいったので、この曲が収録されている「ジョンの魂」を買ったのだった。
また、実質的なジョンのファーストアルバムだったため、まだ内容としてビートルズ色が濃いんじゃないか、と予想したことも理由の一つだ。
とりあえず通しで最後まで聴き、そのヘヴィさに心まで暗くなって、少しこのアルバムを買ったことを後悔したと思う。
しかし、当時としては高価な買い物であるLPレコードは、失敗したからといってすぐ聴かなくなるわけにはいかない。
何度も聴いたら理解できるかも、という思いでとにかく聴き続けたところ、2/3くらいの曲は自分のお気に入りになったのだが、全てを理解するには若すぎた。
ロックとして必要最小限の楽器しか使わず(ときには生ギター1本で)、悲痛な歌詞を叫ぶように唄う一人の男ジョンレノン。
ここには、ビートルズというあまりに重いものを背負ってきたジョンの心の叫び、魂の叫びがある。
若くして母を亡くし、親友を亡くし、デビュー後は非人間的な生活を強いられたジョンは、最愛の妻ヨーコと出会うことによって初めて心の安らぎを得たのだろう。
ようやく心の中にたまっていたものを吐き出し、ここから新たな旅立ちをしようとしていたのかもしれない。
ここにはありのままの裸のジョンレノンがいる。
ビートルズでもなく、愛と平和の人でもなく、自分の内面を語る人。
自己を表現するのに多くの音は必要ない。
オーバーダビングもいらない。
個人的には母への思いをぶちまけた「Mother」、かつての自分へ語りかける「Remember」、そしてあまりにも美しい「Love」がお気に入りだ。
このアルバムの延長線上にあると言われる次作「イマジン」も良いアルバムなのだが、純粋さではこちらに軍配が上がる。
10代の頃、理解しかねたこのアルバムも、ささやかながら人生経験を積んだ現在、どの曲も素直に体に染み渡っていくことに気が付いた。
少しは大人になることが出来たのだろうか。
実質ジョン・レノンのソロ・ファースト・アルバムともいえる「ジョンの魂」
(1970年作品)
「なんて重苦しいアルバムなんだろう」
これがこのアルバムを聴いた初めの感想だった。
このアルバムを初めて聴いたのは15か16の頃。
その頃ビートルズの楽曲は全て聴いたので、次は各メンバーのソロを聴きたいと思ってたのだが、ちょうどラジオでエアチェックした「Love」をとても気にいったので、この曲が収録されている「ジョンの魂」を買ったのだった。
また、実質的なジョンのファーストアルバムだったため、まだ内容としてビートルズ色が濃いんじゃないか、と予想したことも理由の一つだ。
とりあえず通しで最後まで聴き、そのヘヴィさに心まで暗くなって、少しこのアルバムを買ったことを後悔したと思う。
しかし、当時としては高価な買い物であるLPレコードは、失敗したからといってすぐ聴かなくなるわけにはいかない。
何度も聴いたら理解できるかも、という思いでとにかく聴き続けたところ、2/3くらいの曲は自分のお気に入りになったのだが、全てを理解するには若すぎた。
ロックとして必要最小限の楽器しか使わず(ときには生ギター1本で)、悲痛な歌詞を叫ぶように唄う一人の男ジョンレノン。
ここには、ビートルズというあまりに重いものを背負ってきたジョンの心の叫び、魂の叫びがある。
若くして母を亡くし、親友を亡くし、デビュー後は非人間的な生活を強いられたジョンは、最愛の妻ヨーコと出会うことによって初めて心の安らぎを得たのだろう。
ようやく心の中にたまっていたものを吐き出し、ここから新たな旅立ちをしようとしていたのかもしれない。
ここにはありのままの裸のジョンレノンがいる。
ビートルズでもなく、愛と平和の人でもなく、自分の内面を語る人。
自己を表現するのに多くの音は必要ない。
オーバーダビングもいらない。
個人的には母への思いをぶちまけた「Mother」、かつての自分へ語りかける「Remember」、そしてあまりにも美しい「Love」がお気に入りだ。
このアルバムの延長線上にあると言われる次作「イマジン」も良いアルバムなのだが、純粋さではこちらに軍配が上がる。
10代の頃、理解しかねたこのアルバムも、ささやかながら人生経験を積んだ現在、どの曲も素直に体に染み渡っていくことに気が付いた。
少しは大人になることが出来たのだろうか。
| 名盤100選へ戻る |
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
[02/26 take surveys for money]
[02/03 Ahapenij]
[12/18 Blealgagors]
[12/17 BisiomoLofs]
[12/16 Looporwaply]
最新記事
(07/20)
(10/21)
(10/20)
(10/14)
(10/13)
最新TB
プロフィール
HN:
にゅーめん
性別:
男性
趣味:
音楽 読書
自己紹介:
音楽を愛する中年男の叫び
ブログ内検索
忍者アナライズ
