洋楽名盤紹介と日々の雑談を書いてます
第29回ロック名盤シリーズ
今回取り上げるのはフリー「フリー・ライブ!」。
(1971年作品)
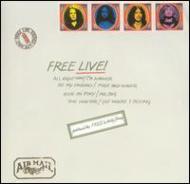
解散直前の1971年に発売されたフリー初のライブ・アルバムだ。
当初は8曲しか入ってなかったようだが、今発売されてるものは、ボーナストラックが入った15曲入り。
ジャケットは上部にメンバーの切手を貼ったみたいなお洒落なデザインだが、人相は極悪だ。
同時期のZEPと同じブリティッシュ・ブルース・ロックの匂い。
これが最初に聴いたときの第一印象である。
ロック・バンドとして必要最小限のユニットであるトリオ演奏。
当然ライブでもサポート・メンバーなしで、3人+ボーカルだけで演奏を行う。
すぐに多くのサポート・メンバーを加えてレコードと出来るだけ同じ音を出そうとするバンドもあるが、ロックバンドたるものメンバーだけで演奏するのが当然だ。
人数が多ければ何でも出来る。
それをバンド・メンバーだけで工夫してライブ・パフォーマンスを行ってこそロック・バンドなのだ。
隙間だらけのサウンド。
しかし薄っぺらさはない。
演奏の強弱をピッキングの強さやドラムを叩く強さで調整し、ここぞというところでバーンと力いっぱい演奏することで爆発力を表現しているからだ。
決してテクニカル集団ではないが、4人が精一杯の力を出し切って演奏しているので気迫が感じられる。
このブルースを基調としたサウンドに花を添えているのが、ポール・コゾフのギターだ。
振れスピードの細かい、ビブラートを中心としたフレーズ展開で、速弾きはほとんどない。
スケールは主にペンタトニックを使ったオーソドックスなもので、味わい深いプレイがファンの多さを納得させる。
7曲目「The Hunter」での迫力ある長いソロプレイ、9曲目「Woman」での殺気立ったプレイなど聴き所は満載だ。
このバンドのブルースを最も楽しめるのは11曲目「Moonshine」だろう。
20歳そこそこの若者が演奏してるとは思えない、人生の酸いも甘いも知り尽くしたかのような熟したプレイ。
ここでのコゾフは、哀愁溢れる魂の叫びのようなギターソロを奏で、ベースも力づくでプレイしているのがよくわかる。
3曲目の「Be My Friend」もとても味わい深いプレイで、ロジャースのソウルフルなボーカルが楽しめる。
バンド・アンサンブルが素晴らしいのは「Mr.Big」だ。
このアルバムには2テイク入っているが、どちらも甲乙付けがたい魅力がある。
曲の後半のベースソロはとてつもなくカッコいい。
こうしたトリオ演奏の理想の一つといえるだろう。
今回取り上げるのはフリー「フリー・ライブ!」。
(1971年作品)
解散直前の1971年に発売されたフリー初のライブ・アルバムだ。
当初は8曲しか入ってなかったようだが、今発売されてるものは、ボーナストラックが入った15曲入り。
ジャケットは上部にメンバーの切手を貼ったみたいなお洒落なデザインだが、人相は極悪だ。
同時期のZEPと同じブリティッシュ・ブルース・ロックの匂い。
これが最初に聴いたときの第一印象である。
ロック・バンドとして必要最小限のユニットであるトリオ演奏。
当然ライブでもサポート・メンバーなしで、3人+ボーカルだけで演奏を行う。
すぐに多くのサポート・メンバーを加えてレコードと出来るだけ同じ音を出そうとするバンドもあるが、ロックバンドたるものメンバーだけで演奏するのが当然だ。
人数が多ければ何でも出来る。
それをバンド・メンバーだけで工夫してライブ・パフォーマンスを行ってこそロック・バンドなのだ。
隙間だらけのサウンド。
しかし薄っぺらさはない。
演奏の強弱をピッキングの強さやドラムを叩く強さで調整し、ここぞというところでバーンと力いっぱい演奏することで爆発力を表現しているからだ。
決してテクニカル集団ではないが、4人が精一杯の力を出し切って演奏しているので気迫が感じられる。
このブルースを基調としたサウンドに花を添えているのが、ポール・コゾフのギターだ。
振れスピードの細かい、ビブラートを中心としたフレーズ展開で、速弾きはほとんどない。
スケールは主にペンタトニックを使ったオーソドックスなもので、味わい深いプレイがファンの多さを納得させる。
7曲目「The Hunter」での迫力ある長いソロプレイ、9曲目「Woman」での殺気立ったプレイなど聴き所は満載だ。
このバンドのブルースを最も楽しめるのは11曲目「Moonshine」だろう。
20歳そこそこの若者が演奏してるとは思えない、人生の酸いも甘いも知り尽くしたかのような熟したプレイ。
ここでのコゾフは、哀愁溢れる魂の叫びのようなギターソロを奏で、ベースも力づくでプレイしているのがよくわかる。
3曲目の「Be My Friend」もとても味わい深いプレイで、ロジャースのソウルフルなボーカルが楽しめる。
バンド・アンサンブルが素晴らしいのは「Mr.Big」だ。
このアルバムには2テイク入っているが、どちらも甲乙付けがたい魅力がある。
曲の後半のベースソロはとてつもなくカッコいい。
こうしたトリオ演奏の理想の一つといえるだろう。
| 名盤100選へ戻る |
PR
第28回名盤シリーズ
今回取り上げるのはヘヴィ・メタルの神ジューダス・プリースト「復讐の叫び」
(1982年作品)

1982年に発表されたこのアルバムは「ヘヴィ・メタルの教科書」とも言われる作品で、後の多くのヘヴィ・メタル・バンドに大きな影響を与えた。
表題の「復讐」(原題はScreaming For Vengeance)とは何に対してなのだろう?
前作「ポイント・オブ・エントリー」の評価がそれほどでもなく「問題作」とされたのに対しての「復讐」だとも言われている。
ただ、アメリカ市場での評価は悪くはなかったようだが。
メンバーはロブ・ハルフォード(vo)、グレンティプトン(g)、K・K・ダウニング(g)、イアン・ヒル(b)、デイブ・ホーランド(ds)。
これが黄金期のメンバーである。
このメンバーによって繰り出される重くメタリックなサウンドは、まさに「ジューダス・プリーストここにあり!」と言わんばかりで、とても堂々としたものだった。
アルバムの冒頭を飾るのは、その後のヘヴィ・メタル界の金字塔ともなった「ヘリオン~エレクトリック・アイ」だ。
今聴いても充分インパクトのあるサウンド。
そして間髪いれずに始まるリフ、まさにヘヴィメタの様式美である。
アルバムのオープニングは、一つの形式として完成させており、後の多くのバンドに影響を与えた。
またライブのオープニングとしてもピッタリで、昨年の来日公演でもオープニングがこれだった。
ほとんどの曲が彼らのオリジナルだが、唯一のカバー曲が「チェインズ」。
彼らのカバー曲はどれもセンスがよく、いつもいい曲を選んでいると思う。
このアルバム中最もハードでスラッシュな曲が表題曲「復讐の叫び」だ。
ここで聴けるロブの鬼のようなシャウト、スピード感溢れるリフ、速いテンポ、どれもが最高で10代の頃はこの曲ばかり繰り返し聴いたものだ。
この曲のツインリードギターがまた素晴らしい。
K・Kのギターソロ、そしてグレンのギターソロ、そしてハーモニー…ここでのハーモニーはすごく複雑に絡んでいて単に低音、高音に分かれてるわけではない。
その2本のギターが奏でるハーモニーはクラシカルに絡み合いながらヘヴィメタの王道を突き進むのだった。
このアルバムは出来るかぎりの大音量で聴きたい。
家の窓を閉め切って許される範囲での最大ボリューム、車なら安全を確保して目一杯ボリュームを上げて聴くべきだ。
そうするとこのアルバムが、なぜヘヴィ・メタルの教科書なのかが自然と理解出来るものと思われる。
今回取り上げるのはヘヴィ・メタルの神ジューダス・プリースト「復讐の叫び」
(1982年作品)
1982年に発表されたこのアルバムは「ヘヴィ・メタルの教科書」とも言われる作品で、後の多くのヘヴィ・メタル・バンドに大きな影響を与えた。
表題の「復讐」(原題はScreaming For Vengeance)とは何に対してなのだろう?
前作「ポイント・オブ・エントリー」の評価がそれほどでもなく「問題作」とされたのに対しての「復讐」だとも言われている。
ただ、アメリカ市場での評価は悪くはなかったようだが。
メンバーはロブ・ハルフォード(vo)、グレンティプトン(g)、K・K・ダウニング(g)、イアン・ヒル(b)、デイブ・ホーランド(ds)。
これが黄金期のメンバーである。
このメンバーによって繰り出される重くメタリックなサウンドは、まさに「ジューダス・プリーストここにあり!」と言わんばかりで、とても堂々としたものだった。
アルバムの冒頭を飾るのは、その後のヘヴィ・メタル界の金字塔ともなった「ヘリオン~エレクトリック・アイ」だ。
今聴いても充分インパクトのあるサウンド。
そして間髪いれずに始まるリフ、まさにヘヴィメタの様式美である。
アルバムのオープニングは、一つの形式として完成させており、後の多くのバンドに影響を与えた。
またライブのオープニングとしてもピッタリで、昨年の来日公演でもオープニングがこれだった。
ほとんどの曲が彼らのオリジナルだが、唯一のカバー曲が「チェインズ」。
彼らのカバー曲はどれもセンスがよく、いつもいい曲を選んでいると思う。
このアルバム中最もハードでスラッシュな曲が表題曲「復讐の叫び」だ。
ここで聴けるロブの鬼のようなシャウト、スピード感溢れるリフ、速いテンポ、どれもが最高で10代の頃はこの曲ばかり繰り返し聴いたものだ。
この曲のツインリードギターがまた素晴らしい。
K・Kのギターソロ、そしてグレンのギターソロ、そしてハーモニー…ここでのハーモニーはすごく複雑に絡んでいて単に低音、高音に分かれてるわけではない。
その2本のギターが奏でるハーモニーはクラシカルに絡み合いながらヘヴィメタの王道を突き進むのだった。
このアルバムは出来るかぎりの大音量で聴きたい。
家の窓を閉め切って許される範囲での最大ボリューム、車なら安全を確保して目一杯ボリュームを上げて聴くべきだ。
そうするとこのアルバムが、なぜヘヴィ・メタルの教科書なのかが自然と理解出来るものと思われる。
| 名盤100選へ戻る |
第27回名盤シリーズ
今回はカンタベリー・ロックの大御所キャラバンの「グレイとピンクの地」。
(1971年作品)
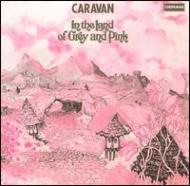
今回取り上げるアルバムは他のアルバムのように数百万枚売れたとか、全米No.1になったアルバムではない。
地味にゴールドディスクは取得しているが、一般的には知られていないアルバムかもしれない。
しかし、カンタベリー・ロックを語る上で欠かせないアルバムであり、今もマニアを中心に根強いファンがいるのも事実だ。
71年に発表されたこのアルバムはキャラバンの2枚目のアルバムで、メンバーはパイ・ヘイスティング(g、vo)、リチャード・シンクレア(b、vo)、デヴィッド・シンクレア(key)、リチャード・コフラン(ds)だ。
他にゲストとしてジミー・ヘイスティング、デヴィッド・グリンステッド、などが参加している。
作品は非常に親しみ易くポップな曲と、長いインストパートが続く演奏重視の難解な曲の2つの面がある。
ポップな面については旧LP時代のA面がそれに当たる。
トロンボーンを使ったなんともホノボノとしたイントロで始まるゴルフ・ガール。
天気の良い暇な午後の休日に、ノンビリとゴルフを楽しむ風景が広がるような曲だ。
リチャードの押さえたボーカルがとてもいい雰囲気を醸し出しており、アコースティックなサウンドとフルートがさらにノホホンとしたイメージを形作っている。
サビのメロディを聴くと、ポップでホノボノしていても、少しスパイスが効いてる感じがするのが面白い。
4曲目の表題曲も同じくホノボノ路線の曲。
ゆったり心地よいリズムで、リチャードが得意の低音ボーカルを聴かせる。
ここでの彼のボーカル・スタイルは完全に彼独自のもので、「グビュドゥビドゥブブブブビヴゥヴ~~」と文字で表現出来ないような歌い方。
彼はこれを自分のスタイルとしているようで、キャラバン脱退後のハットフィールド&ザ・ノースでもこの歌い方をしている。
ただ、あまり成功しているように思えないのだが。
この曲も、微妙に変拍子を使ったりしてただのポップ・ソングにはなっていない。
インストパートを重視したのは、旧LPのB面全てを使った22分におよぶ「9フィートのアンダーグラウンド」だ。
歪んだ独特のオルガンサウンドで前半をひっぱる。
決してクリムゾンやイエスのように緊張感溢れるサウンドではなく、あくまでもゆったりと聴かせてくれるのが彼らの特徴だ。
途中からサックスも入って、ジャズロック風のカラーを推し進めていく。
前半のボーカルを決めるのはパイ・ヘイスティングの高音ボーカル、リチャードとは違った味がある。
その後、静かなパートに入り大砲の音ともに曲調が一変、ゆったりした雰囲気はなくなり、シリアスな方向へ。
リチャードの暗いボーカルが入るとさらに曲はダークで物悲しいイメージに統一され、次のキメのパートへ繋がる。
最後はテンポも速くなって終了、ジャケで表されているピンクの世界の旅は終わる。
現在のCDではボーナストラックが5曲入っていて、「ゴルフ・ガール」の前身「グループ・ガール」や、パイの魅力的なギターソロが聴ける「9フィート~」のヴァージョン違いなどが聴けてお買い得である。
今回はカンタベリー・ロックの大御所キャラバンの「グレイとピンクの地」。
(1971年作品)
今回取り上げるアルバムは他のアルバムのように数百万枚売れたとか、全米No.1になったアルバムではない。
地味にゴールドディスクは取得しているが、一般的には知られていないアルバムかもしれない。
しかし、カンタベリー・ロックを語る上で欠かせないアルバムであり、今もマニアを中心に根強いファンがいるのも事実だ。
71年に発表されたこのアルバムはキャラバンの2枚目のアルバムで、メンバーはパイ・ヘイスティング(g、vo)、リチャード・シンクレア(b、vo)、デヴィッド・シンクレア(key)、リチャード・コフラン(ds)だ。
他にゲストとしてジミー・ヘイスティング、デヴィッド・グリンステッド、などが参加している。
作品は非常に親しみ易くポップな曲と、長いインストパートが続く演奏重視の難解な曲の2つの面がある。
ポップな面については旧LP時代のA面がそれに当たる。
トロンボーンを使ったなんともホノボノとしたイントロで始まるゴルフ・ガール。
天気の良い暇な午後の休日に、ノンビリとゴルフを楽しむ風景が広がるような曲だ。
リチャードの押さえたボーカルがとてもいい雰囲気を醸し出しており、アコースティックなサウンドとフルートがさらにノホホンとしたイメージを形作っている。
サビのメロディを聴くと、ポップでホノボノしていても、少しスパイスが効いてる感じがするのが面白い。
4曲目の表題曲も同じくホノボノ路線の曲。
ゆったり心地よいリズムで、リチャードが得意の低音ボーカルを聴かせる。
ここでの彼のボーカル・スタイルは完全に彼独自のもので、「グビュドゥビドゥブブブブビヴゥヴ~~」と文字で表現出来ないような歌い方。
彼はこれを自分のスタイルとしているようで、キャラバン脱退後のハットフィールド&ザ・ノースでもこの歌い方をしている。
ただ、あまり成功しているように思えないのだが。
この曲も、微妙に変拍子を使ったりしてただのポップ・ソングにはなっていない。
インストパートを重視したのは、旧LPのB面全てを使った22分におよぶ「9フィートのアンダーグラウンド」だ。
歪んだ独特のオルガンサウンドで前半をひっぱる。
決してクリムゾンやイエスのように緊張感溢れるサウンドではなく、あくまでもゆったりと聴かせてくれるのが彼らの特徴だ。
途中からサックスも入って、ジャズロック風のカラーを推し進めていく。
前半のボーカルを決めるのはパイ・ヘイスティングの高音ボーカル、リチャードとは違った味がある。
その後、静かなパートに入り大砲の音ともに曲調が一変、ゆったりした雰囲気はなくなり、シリアスな方向へ。
リチャードの暗いボーカルが入るとさらに曲はダークで物悲しいイメージに統一され、次のキメのパートへ繋がる。
最後はテンポも速くなって終了、ジャケで表されているピンクの世界の旅は終わる。
現在のCDではボーナストラックが5曲入っていて、「ゴルフ・ガール」の前身「グループ・ガール」や、パイの魅力的なギターソロが聴ける「9フィート~」のヴァージョン違いなどが聴けてお買い得である。
| 名盤100選へ戻る |
第26回名盤シリーズ
今回はAC/DCの「バック・イン・ブラック」。
(1980年作品)
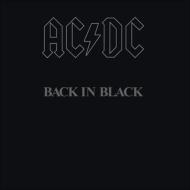
前作「地獄のハイウェイ」までボーカルだったボン・スコットの突然の死により、一時は解散説も流れたAC/DCだが、さらにパワー・アップして80年に発表されたアルバムがこれだ。
メンバーはアンガス・ヤング(g)、マルコム・ヤング(g)、フィル・ラッド(ds)、クリフ・ウイリアムズ(b)、ブライアン・ジョンソン(vo)。
アルバム全体を貫く張り詰めた空気感、硬質で荒っぽいギター・サウンド、リフ主体でメロディ感が少ない印象。
まさに男のロック!
軟弱者は相手にしていないのだ。
それはこのアルバムから参加したブライアンの切り裂くようなボーカルにも現れている。
飾り気が全くなく、贅肉を削ぎ落とした硬派のロックだが、これが全世界で大ヒットした。
アルバムの売り上げは半端ではなく、ポピュラー音楽史上に残る大名盤でありながら、日本では硬派すぎる印象のためか人気なし。
そのため凄まじいライブパフォーマンスを行うバンドなのに滅多に日本に来ないのは、まことに残念なことだ。
冒頭から鐘の音が鳴り響く。
これは世界制覇を目前にして突然の死を迎えた前ボーカル、ボン・スコットへ捧げられたものだ。
ミディアムテンポのリズムにコード・ワークを主体としたギター・リフ。
キーボードはもちろんオーバー・ダビングすらないのでは?と思わせるシンプルなサウンドだが、これが底知れぬ破壊力を生むのだった。
ドラムはただエイトビートを刻み、ベースはひたすらルート音を8部で弾きつづける。
リズムギターはひたすら同じリフを繰り返し、しかしこれだけシンプルなのに物凄いノリ。
これはもうAC/DCにしか出来ない芸当だ。
そして強固なリズム隊に支えられた土台の上をアンガスのギターが暴れまくりる。
ステージでは半ズボンにランドセルというスクール・ボーイ・スタイルで登場し、そのうち上半身裸になって気が狂ったように弾きまくる彼だが、このアルバムでもその断片を垣間見ることが出来る。
このあたりが前作までと違って、ライブ・パフォーマンスの美味しい部分が上手くスタジオで表現されているところだ。
凶暴でワイルドなキャラだった前任者と違い、まるで競馬場や酒場にいるような「オッサンキャラ」なブライアンだが、表現の幅が広がって少しだけメロディアスな部分もある。
それが顕著に現れているのが「You Shook Me All Night Long」と「Rock And Roll Ain't Noise Pollution 」あたりだろう。
ポップとは程遠い彼らだが、これらの曲には親しみ易さがありAC/DC嫌いな人でもこれだけは好き、という人もいるくらいだ。
次のアルバム「悪魔の招待状」で全米1位を記録し、名実ともにトップバンドになる彼らだが、その勢いは衰えることを知らず最強のライブバンドとして現在も活躍している。
今回はAC/DCの「バック・イン・ブラック」。
(1980年作品)
前作「地獄のハイウェイ」までボーカルだったボン・スコットの突然の死により、一時は解散説も流れたAC/DCだが、さらにパワー・アップして80年に発表されたアルバムがこれだ。
メンバーはアンガス・ヤング(g)、マルコム・ヤング(g)、フィル・ラッド(ds)、クリフ・ウイリアムズ(b)、ブライアン・ジョンソン(vo)。
アルバム全体を貫く張り詰めた空気感、硬質で荒っぽいギター・サウンド、リフ主体でメロディ感が少ない印象。
まさに男のロック!
軟弱者は相手にしていないのだ。
それはこのアルバムから参加したブライアンの切り裂くようなボーカルにも現れている。
飾り気が全くなく、贅肉を削ぎ落とした硬派のロックだが、これが全世界で大ヒットした。
アルバムの売り上げは半端ではなく、ポピュラー音楽史上に残る大名盤でありながら、日本では硬派すぎる印象のためか人気なし。
そのため凄まじいライブパフォーマンスを行うバンドなのに滅多に日本に来ないのは、まことに残念なことだ。
冒頭から鐘の音が鳴り響く。
これは世界制覇を目前にして突然の死を迎えた前ボーカル、ボン・スコットへ捧げられたものだ。
ミディアムテンポのリズムにコード・ワークを主体としたギター・リフ。
キーボードはもちろんオーバー・ダビングすらないのでは?と思わせるシンプルなサウンドだが、これが底知れぬ破壊力を生むのだった。
ドラムはただエイトビートを刻み、ベースはひたすらルート音を8部で弾きつづける。
リズムギターはひたすら同じリフを繰り返し、しかしこれだけシンプルなのに物凄いノリ。
これはもうAC/DCにしか出来ない芸当だ。
そして強固なリズム隊に支えられた土台の上をアンガスのギターが暴れまくりる。
ステージでは半ズボンにランドセルというスクール・ボーイ・スタイルで登場し、そのうち上半身裸になって気が狂ったように弾きまくる彼だが、このアルバムでもその断片を垣間見ることが出来る。
このあたりが前作までと違って、ライブ・パフォーマンスの美味しい部分が上手くスタジオで表現されているところだ。
凶暴でワイルドなキャラだった前任者と違い、まるで競馬場や酒場にいるような「オッサンキャラ」なブライアンだが、表現の幅が広がって少しだけメロディアスな部分もある。
それが顕著に現れているのが「You Shook Me All Night Long」と「Rock And Roll Ain't Noise Pollution 」あたりだろう。
ポップとは程遠い彼らだが、これらの曲には親しみ易さがありAC/DC嫌いな人でもこれだけは好き、という人もいるくらいだ。
次のアルバム「悪魔の招待状」で全米1位を記録し、名実ともにトップバンドになる彼らだが、その勢いは衰えることを知らず最強のライブバンドとして現在も活躍している。
| 名盤100選へ戻る |
第25回名盤シリーズ
今回はキャロル・キング「つづれおり」。
(1971年作品)
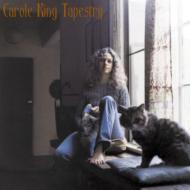
1971年に発表されたシンガー・ソングライター、キャロル・キングの2枚目のソロアルバムである。
彼女が音楽界で活動を始めるのはけっこう古く、ビートルズのデビュー前からだ。
当初はプロのソングライターとしてシュレルズの「WILL YOU BE LOVE ME TOMOLLOW」など大ヒット曲を次々に書き上げる才能の持ち主。
とにかく作曲家としての実績は相当なもので1961年だけでも12曲ものヒット曲を書いている。
またキーボード・プレイヤーとしても数多くのセッションに参加し、B.B.キングのアルバムなどにも彼女のクレジットを見ることが出来るようだ。
そんな彼女が作ったソロアルバム、悪いわけがない。
どこを切っても素晴らしいメロディが詰まっており、まさに美メロの玉手箱だ。
現代の音楽を聴きなれた耳からすれば、シンプルでスカスカなサウンド。
それも生ピアノとアコギを中心としたアコースティックなバックに、少し枯れた味わいのキャロルのボーカル。
それでも繰り返し聴けば聴くほど味わいが増す、まさに「スルメ」なアルバムです。
ほとんどの曲がこのアルバムのために書き下ろされた新曲だが、過去に他のシンガーやコーラス・グループのために書いた曲のセルフカバーも収められている。
前述のシュレルズの曲などは、それよりもスローで大人びた味わいに仕上がっているのが面白い。
個人的には「IT'S TOO LATE」の別れを決意し、明日への希望を感じさせるメロディラインに古き良きオールディーズの匂いを感じる。
また「WAY OVER YONDER」の気だるい雰囲気の中で幸福への道を探す内容をしっとりと歌い上げる様に、ちょっと切ない人生とそれでも前向きに生きようとする心構えが見られる。
このアルバムを聴くととてもやさしい気持ちになれるような気がする。
「良質のポップス」
そんな言葉が似合う、決して派手ではない、しかしキラリと光る名曲の数々。
秋の夜長にじっくりと聴きたいアルバムだ。
今回はキャロル・キング「つづれおり」。
(1971年作品)
1971年に発表されたシンガー・ソングライター、キャロル・キングの2枚目のソロアルバムである。
彼女が音楽界で活動を始めるのはけっこう古く、ビートルズのデビュー前からだ。
当初はプロのソングライターとしてシュレルズの「WILL YOU BE LOVE ME TOMOLLOW」など大ヒット曲を次々に書き上げる才能の持ち主。
とにかく作曲家としての実績は相当なもので1961年だけでも12曲ものヒット曲を書いている。
またキーボード・プレイヤーとしても数多くのセッションに参加し、B.B.キングのアルバムなどにも彼女のクレジットを見ることが出来るようだ。
そんな彼女が作ったソロアルバム、悪いわけがない。
どこを切っても素晴らしいメロディが詰まっており、まさに美メロの玉手箱だ。
現代の音楽を聴きなれた耳からすれば、シンプルでスカスカなサウンド。
それも生ピアノとアコギを中心としたアコースティックなバックに、少し枯れた味わいのキャロルのボーカル。
それでも繰り返し聴けば聴くほど味わいが増す、まさに「スルメ」なアルバムです。
ほとんどの曲がこのアルバムのために書き下ろされた新曲だが、過去に他のシンガーやコーラス・グループのために書いた曲のセルフカバーも収められている。
前述のシュレルズの曲などは、それよりもスローで大人びた味わいに仕上がっているのが面白い。
個人的には「IT'S TOO LATE」の別れを決意し、明日への希望を感じさせるメロディラインに古き良きオールディーズの匂いを感じる。
また「WAY OVER YONDER」の気だるい雰囲気の中で幸福への道を探す内容をしっとりと歌い上げる様に、ちょっと切ない人生とそれでも前向きに生きようとする心構えが見られる。
このアルバムを聴くととてもやさしい気持ちになれるような気がする。
「良質のポップス」
そんな言葉が似合う、決して派手ではない、しかしキラリと光る名曲の数々。
秋の夜長にじっくりと聴きたいアルバムだ。
| 名盤100選へ戻る |
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
[02/26 take surveys for money]
[02/03 Ahapenij]
[12/18 Blealgagors]
[12/17 BisiomoLofs]
[12/16 Looporwaply]
最新記事
(07/20)
(10/21)
(10/20)
(10/14)
(10/13)
最新TB
プロフィール
HN:
にゅーめん
性別:
男性
趣味:
音楽 読書
自己紹介:
音楽を愛する中年男の叫び
ブログ内検索
忍者アナライズ
