洋楽名盤紹介と日々の雑談を書いてます
ノーメイク時代のキッスを支えたミュージシャンたち
第3回ブルース・キューリックと「クレイジー・ナイト」
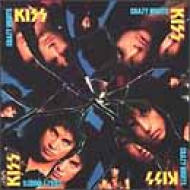
前任ギタリストが奇病のため、代替ギタリストとしてステージに立ったブルース・キューリックが、そのまま新ギタリストになる。
アルバム「アサイラム」発表後、ツアーも行い、それなりに反響を得るのだが、70年代の黄金期の勢いには程遠く、再びKISSは迷いはじめる。
そのままメタル路線を突き進むのかと思いきや、今度はヴァン・ヘイレンを意識したような路線でやってきたのだ。
どんなギターもそつなくこなす、それが可能なのが、ブルース・キューリックというギタリストなのだった。

個性豊かなエースやヴィニーと違い、やや器用貧乏なところのあるブルース。
彼はすごく上手い、良くも悪くも一流スタジオ・ミュージシャンのようだ。
だから何でも弾ける。
もちろん、ヴァン・ヘイレンみたいなギターを弾けといわれれば、難なくこなす。
ボン・ジョビみたいなギターを弾けと言われれば、問題なく弾く。
決して目立とうとはせず、いつもポール、ジーンの裏方に徹しているのだが、それが長年KISSを支えたわりに、人気が薄いところなんだろう。
おそらく、人間としてはすごくいい人だと思う。
このアルバムは隠れた人気アルバムだと言われている。
個人的にはそれほど優れたアルバムとは思わないが。
前作「アサイラム」の方が好きなのだが、ブルースのギター・スタイルという点で、あえてこちらを選んだ。
楽曲的には、ポールが活躍していて、なかなかのメロディアス・ハード・ロック・アルバムに仕上がっている。
ブルースの凄さがよくわかるのが、4曲目「ノー・ノー・ノー」だ。
出だしから圧倒される凄まじさ。
これを聴くとブルースってやはり上手いんだなと痛感する。
ヴァン・ヘイレンを意識してると思うのだが、俺達だって本気になればこれくらい出来るんだ、と言ってる気がする。
カテゴリー一覧
ホーム
第3回ブルース・キューリックと「クレイジー・ナイト」
前任ギタリストが奇病のため、代替ギタリストとしてステージに立ったブルース・キューリックが、そのまま新ギタリストになる。
アルバム「アサイラム」発表後、ツアーも行い、それなりに反響を得るのだが、70年代の黄金期の勢いには程遠く、再びKISSは迷いはじめる。
そのままメタル路線を突き進むのかと思いきや、今度はヴァン・ヘイレンを意識したような路線でやってきたのだ。
どんなギターもそつなくこなす、それが可能なのが、ブルース・キューリックというギタリストなのだった。
個性豊かなエースやヴィニーと違い、やや器用貧乏なところのあるブルース。
彼はすごく上手い、良くも悪くも一流スタジオ・ミュージシャンのようだ。
だから何でも弾ける。
もちろん、ヴァン・ヘイレンみたいなギターを弾けといわれれば、難なくこなす。
ボン・ジョビみたいなギターを弾けと言われれば、問題なく弾く。
決して目立とうとはせず、いつもポール、ジーンの裏方に徹しているのだが、それが長年KISSを支えたわりに、人気が薄いところなんだろう。
おそらく、人間としてはすごくいい人だと思う。
このアルバムは隠れた人気アルバムだと言われている。
個人的にはそれほど優れたアルバムとは思わないが。
前作「アサイラム」の方が好きなのだが、ブルースのギター・スタイルという点で、あえてこちらを選んだ。
楽曲的には、ポールが活躍していて、なかなかのメロディアス・ハード・ロック・アルバムに仕上がっている。
ブルースの凄さがよくわかるのが、4曲目「ノー・ノー・ノー」だ。
出だしから圧倒される凄まじさ。
これを聴くとブルースってやはり上手いんだなと痛感する。
ヴァン・ヘイレンを意識してると思うのだが、俺達だって本気になればこれくらい出来るんだ、と言ってる気がする。
カテゴリー一覧
ホーム
PR
第36回名盤シリーズ
今回はクイーンの傑作アルバム「オペラ座の夜」。
(1975年作品)
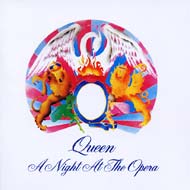
私が初めて聴いたクイーンのアルバムは、「ホット・スペース」というダンス色の濃いレコードだった。
当時の最新アルバムで、けっこう良いアルバムだと思ったが、ファンの間では人気ないようだ。
それから1stアルバム、2ndアルバムと聴いて、とくに1stアルバムは気に入った。
そして、次は名盤の誉れ高い「オペラ座の夜」を買おう!と思い、レコード屋へ行ったのだが、売ってなかったので、仕方なく「ジャズ」というアルバムを購入。
でもこのアルバムは好きになれず、クイーンから遠ざかることになった。
その後、今回話題にする「オペラ座の夜」を聴くことになるのですが、なんと「ジャズ」を買ってから20年近くたってからだ。
もし、あのときレコード屋にこのアルバムがあれば、迷わず買っていたはずだし、クイーンにはまっていた可能性もある。
クイーンっていいバンドなんだなっていう、今更なことを改めて認識したのだった。
やはり、各曲がそれぞれバラエティ豊かで、個性的で、完成度が非常に高い。
よくオペラとロックの融合などと形容されるが、普通に曲の出来、アレンジの出来が素晴らしいんだと思う。
初期のクイーンはハードロック・バンドとして括られることが多いのだが、この4枚目のアルバムにハードロック色は少なく、印象としては通常のブリティッシュ・ロック・バンドだ。
しかし普通じゃないのは、この斬新なアレンジ力だろう。
とくに抜きん出ているのは名曲「ボヘミアン・ラプソディ」。
「20世紀で最も偉大な曲」とも言われる、このオペラ的な曲の完成度はどうだ。
オープニングのコーラスワークにピアノが絡んでくるところから、ゾクゾクと期待感が高まってくる。
メロディの素晴らしさもさることながら、アレンジ力の凄さがこの曲のレベルを飛躍的にあげていることは間違いない。
ただ、「ボヘミアン~」だけがこのアルバムの魅力ではない。
「ボヘミアン~」が偉大すぎるために、他の曲の評価があまりされてないようなので、いくつか個人的に好きな曲を紹介しよう。
1曲目の「 Death on Two Legs 」はハードなロックっぽい曲だ。
私はこの曲は、サビがとくに良いと思う。
サビのコーラスワーク、とくに最高音の声がキャッチーでいい。
ブライアン・メイのギターは、ここでも独特のこもったサウンドを聴かせてくれる。
4曲目の「You're My Best Friend 」はメロディアスでポップな曲。
エレキ・ピアノの音色がなんとも印象的で、フレディの思い入れタップリのボーカルとコーラスワークが乗ると、なんとも素直にいい曲だなって感じることが出来る。
ここでのドラムも、適度なオカズが心地よい。
5曲目の「'39」はカントリーっぽい曲。
アコギのストロークが良いのは当然だが、やはりこのバスドラだけによるノリがホノボノとしていい。
ここでも素晴らしいコーラスワークが楽しめる。
ノスタルジックでちょっぴり哀愁漂う名曲だ。
7曲目の「 Seaside Rendezvous 」は楽しいポップな曲だ。
こういうタイプの曲ってなんていうんだろう?
お洒落で、楽しくって、踊りだしたくなるような曲なのだ。
こんな曲をサラッとやってしまうあたり、やはり只者ではない。
今回はクイーンの傑作アルバム「オペラ座の夜」。
(1975年作品)
私が初めて聴いたクイーンのアルバムは、「ホット・スペース」というダンス色の濃いレコードだった。
当時の最新アルバムで、けっこう良いアルバムだと思ったが、ファンの間では人気ないようだ。
それから1stアルバム、2ndアルバムと聴いて、とくに1stアルバムは気に入った。
そして、次は名盤の誉れ高い「オペラ座の夜」を買おう!と思い、レコード屋へ行ったのだが、売ってなかったので、仕方なく「ジャズ」というアルバムを購入。
でもこのアルバムは好きになれず、クイーンから遠ざかることになった。
その後、今回話題にする「オペラ座の夜」を聴くことになるのですが、なんと「ジャズ」を買ってから20年近くたってからだ。
もし、あのときレコード屋にこのアルバムがあれば、迷わず買っていたはずだし、クイーンにはまっていた可能性もある。
クイーンっていいバンドなんだなっていう、今更なことを改めて認識したのだった。
やはり、各曲がそれぞれバラエティ豊かで、個性的で、完成度が非常に高い。
よくオペラとロックの融合などと形容されるが、普通に曲の出来、アレンジの出来が素晴らしいんだと思う。
初期のクイーンはハードロック・バンドとして括られることが多いのだが、この4枚目のアルバムにハードロック色は少なく、印象としては通常のブリティッシュ・ロック・バンドだ。
しかし普通じゃないのは、この斬新なアレンジ力だろう。
とくに抜きん出ているのは名曲「ボヘミアン・ラプソディ」。
「20世紀で最も偉大な曲」とも言われる、このオペラ的な曲の完成度はどうだ。
オープニングのコーラスワークにピアノが絡んでくるところから、ゾクゾクと期待感が高まってくる。
メロディの素晴らしさもさることながら、アレンジ力の凄さがこの曲のレベルを飛躍的にあげていることは間違いない。
ただ、「ボヘミアン~」だけがこのアルバムの魅力ではない。
「ボヘミアン~」が偉大すぎるために、他の曲の評価があまりされてないようなので、いくつか個人的に好きな曲を紹介しよう。
1曲目の「 Death on Two Legs 」はハードなロックっぽい曲だ。
私はこの曲は、サビがとくに良いと思う。
サビのコーラスワーク、とくに最高音の声がキャッチーでいい。
ブライアン・メイのギターは、ここでも独特のこもったサウンドを聴かせてくれる。
4曲目の「You're My Best Friend 」はメロディアスでポップな曲。
エレキ・ピアノの音色がなんとも印象的で、フレディの思い入れタップリのボーカルとコーラスワークが乗ると、なんとも素直にいい曲だなって感じることが出来る。
ここでのドラムも、適度なオカズが心地よい。
5曲目の「'39」はカントリーっぽい曲。
アコギのストロークが良いのは当然だが、やはりこのバスドラだけによるノリがホノボノとしていい。
ここでも素晴らしいコーラスワークが楽しめる。
ノスタルジックでちょっぴり哀愁漂う名曲だ。
7曲目の「 Seaside Rendezvous 」は楽しいポップな曲だ。
こういうタイプの曲ってなんていうんだろう?
お洒落で、楽しくって、踊りだしたくなるような曲なのだ。
こんな曲をサラッとやってしまうあたり、やはり只者ではない。
| 名盤100選へ戻る |
ノーメイク時代のキッスを支えたミュージシャンたち
第2回マーク・セント・ジョンと「アニマライズ」
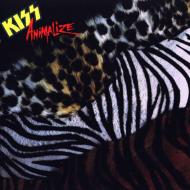
前任ギタリスト、ヴィニー・ヴィンセントはツアー終了と共に脱退。
替わりに入ったのは、マーク・セント・ジョンという人物。
彼のギター・テクニックはヴィニーと比べても決して劣らない、80年代的スーパー・ギタリストだ。
ギター・スタイルはアームを積極的に利用するタイプと言えるかもしれない。
もちろん速弾きも得意分野で、エースでは絶対に弾かないようなテクニカルな超速弾きをあっさりと決める。
どちらかというとハンマリング・プリングを多用するタイプで、トリル+アームが得意技のようだ。
ただし、エースやヴィニーと違い作曲面での貢献はなかったようだが。

しかし、これで順風満帆とはいかず、またしても危機が訪れる。
マークはレイターズ・シンドロームという奇病に侵され、手が動かなくなってしまったのだった。
アルバムのレコーディングが終了して、ツアーに出かけるのだが、すぐにライブが出来ない状態に陥り、慌てて代替ギタリストをツアーに動向させる。
選ばれたのは、後にキッスのギタリストになるブルース・キューリックだ。
調子の良い日はなんとかマークがステージに立つこともあったようだが、そんな不安定な状況が長続きするはずもなく、脱退することになった。
そんなマークの唯一のKISS参加作品が、この「アニマライズ」である。
このアルバムの代表曲と言えば、ライブの定番曲「へヴンズ・オン・ファイヤー」だろう。
この曲は70年代KISSを彷彿させる、ロックンロール風の曲だ。
しかし、このアルバム、そしてこの時期っぽいのは1曲目「アイヴ・ハド・イナフ」などのハードな曲だと思う。
かなりヘヴィ・メタルしてて、ハード・ドライヴィングなナンバーだ。
ギター・ソロは弾きまくりタイプで、とにかく熱い。
シングルにもなった「スリル・イン・ザ・ナイト」も傑曲だが、ジーンが歌う「ホワイル・ザ・シティ・スリープス」が個人的に好きだ。
この曲のリフも今までのKISSにはなかったタイプで、80年代LAメタルに多いミディアム・テンポのカッコイイ曲に仕上がっている。
カテゴリー一覧
ホーム
第2回マーク・セント・ジョンと「アニマライズ」
前任ギタリスト、ヴィニー・ヴィンセントはツアー終了と共に脱退。
替わりに入ったのは、マーク・セント・ジョンという人物。
彼のギター・テクニックはヴィニーと比べても決して劣らない、80年代的スーパー・ギタリストだ。
ギター・スタイルはアームを積極的に利用するタイプと言えるかもしれない。
もちろん速弾きも得意分野で、エースでは絶対に弾かないようなテクニカルな超速弾きをあっさりと決める。
どちらかというとハンマリング・プリングを多用するタイプで、トリル+アームが得意技のようだ。
ただし、エースやヴィニーと違い作曲面での貢献はなかったようだが。
しかし、これで順風満帆とはいかず、またしても危機が訪れる。
マークはレイターズ・シンドロームという奇病に侵され、手が動かなくなってしまったのだった。
アルバムのレコーディングが終了して、ツアーに出かけるのだが、すぐにライブが出来ない状態に陥り、慌てて代替ギタリストをツアーに動向させる。
選ばれたのは、後にキッスのギタリストになるブルース・キューリックだ。
調子の良い日はなんとかマークがステージに立つこともあったようだが、そんな不安定な状況が長続きするはずもなく、脱退することになった。
そんなマークの唯一のKISS参加作品が、この「アニマライズ」である。
このアルバムの代表曲と言えば、ライブの定番曲「へヴンズ・オン・ファイヤー」だろう。
この曲は70年代KISSを彷彿させる、ロックンロール風の曲だ。
しかし、このアルバム、そしてこの時期っぽいのは1曲目「アイヴ・ハド・イナフ」などのハードな曲だと思う。
かなりヘヴィ・メタルしてて、ハード・ドライヴィングなナンバーだ。
ギター・ソロは弾きまくりタイプで、とにかく熱い。
シングルにもなった「スリル・イン・ザ・ナイト」も傑曲だが、ジーンが歌う「ホワイル・ザ・シティ・スリープス」が個人的に好きだ。
この曲のリフも今までのKISSにはなかったタイプで、80年代LAメタルに多いミディアム・テンポのカッコイイ曲に仕上がっている。
カテゴリー一覧
ホーム
第35回名盤シリーズ
今回は、ウィッシュボーン・アッシュ「百眼の巨人アーガス」
(1972年作品)
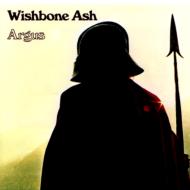
ウィッシュボーン・アッシュは、私より少しだけ上の世代の人にとって、とても重要なバンドで、ツインリードといえばウィッシュボーン・アッシュと真っ先に思い浮かぶバンドらしい。
それまで、一つのバンドにギタリストが2人いるバンドは珍しくはなかったが、その大半はリードギターとリズムギターと役割分担がはっきりしていたのだった。
しかし、このバンドは2人のギタリストが共にリードギタリストであり、曲によってギターソロを引き分けるだけでなく、美しいハーモニーを弾くこともあり、当時としては新しい試みだったようである。
彼らよりも前にヤードバーズなどで、ジェフ・ベックとジミー・ペイジがツインリードとして在籍していた時期もありましたが、時期は短くバンドとしての個性にはなってないように思う。
さて、この「百眼の巨人アーガス」を聴いて最初に感じたのは「以外に大人しい」ということだ。
同じく最初期のツインリード・バンドにオールマン・ブラザーズ・バンドがありますが、彼らはアメリカン・バンドらしい豪快さなブルース・ロックだった。
そんな彼らと比較すると非常に線が細く、フォーク的な印象を持ったのだった。
しかし繊細とも言える彼らのサウンドは実にブリティッシュ・ロックらしく、メロディ・ラインの美しさは彼らの特徴の一つといえる。
アンディ・パウエルとテッド・ターナーの2人のリード・ギタリストは、この時期の他のギタリスト同様、ペンタトニック・スケールを多用したギター・スタイルだ。
速弾きなどのテクニカルな奏法はほとんどやらない。
しかし流れるようなフレーズを、湧き出る泉のごとく弾きだすのは、かなりのセンスの持ち主であることは間違いない。
また美しいアルペジオ・フレーズを多用しているのも特徴の一つかもしれない。
フォーク・トラッドの影響がこういうところにも現れていて、メロディの美しさをより引き立てることに成功している。
このアルバムからのお気に入りですが、2曲目「いつか世界は」、前半は大人のムード溢れる切ないバラードだが、途中からアップテンポになり曲調が替わる。
ここでまず注目すべきは、マーティン・ターナーによるベース・ラインだ。
これはかなりスゴイ。
私はこれを聴くとベースが弾きたくなる。
そして後半の長いギター・ソロも聴き所満載だ。
そして7曲目「剣を捨てろ」。
アルバムのラストを飾るに相応しい、壮大で感動的な曲。
後半のツイン・ギターがハモッてるようで、微妙に違うフレーズを弾いているのだが、異なるメロディを同時に演奏して一つの音楽にするっていのは、構想としては他にもあったと思うが、ここまで完成させている例は珍しいと思う。
今回は、ウィッシュボーン・アッシュ「百眼の巨人アーガス」
(1972年作品)
ウィッシュボーン・アッシュは、私より少しだけ上の世代の人にとって、とても重要なバンドで、ツインリードといえばウィッシュボーン・アッシュと真っ先に思い浮かぶバンドらしい。
それまで、一つのバンドにギタリストが2人いるバンドは珍しくはなかったが、その大半はリードギターとリズムギターと役割分担がはっきりしていたのだった。
しかし、このバンドは2人のギタリストが共にリードギタリストであり、曲によってギターソロを引き分けるだけでなく、美しいハーモニーを弾くこともあり、当時としては新しい試みだったようである。
彼らよりも前にヤードバーズなどで、ジェフ・ベックとジミー・ペイジがツインリードとして在籍していた時期もありましたが、時期は短くバンドとしての個性にはなってないように思う。
さて、この「百眼の巨人アーガス」を聴いて最初に感じたのは「以外に大人しい」ということだ。
同じく最初期のツインリード・バンドにオールマン・ブラザーズ・バンドがありますが、彼らはアメリカン・バンドらしい豪快さなブルース・ロックだった。
そんな彼らと比較すると非常に線が細く、フォーク的な印象を持ったのだった。
しかし繊細とも言える彼らのサウンドは実にブリティッシュ・ロックらしく、メロディ・ラインの美しさは彼らの特徴の一つといえる。
アンディ・パウエルとテッド・ターナーの2人のリード・ギタリストは、この時期の他のギタリスト同様、ペンタトニック・スケールを多用したギター・スタイルだ。
速弾きなどのテクニカルな奏法はほとんどやらない。
しかし流れるようなフレーズを、湧き出る泉のごとく弾きだすのは、かなりのセンスの持ち主であることは間違いない。
また美しいアルペジオ・フレーズを多用しているのも特徴の一つかもしれない。
フォーク・トラッドの影響がこういうところにも現れていて、メロディの美しさをより引き立てることに成功している。
このアルバムからのお気に入りですが、2曲目「いつか世界は」、前半は大人のムード溢れる切ないバラードだが、途中からアップテンポになり曲調が替わる。
ここでまず注目すべきは、マーティン・ターナーによるベース・ラインだ。
これはかなりスゴイ。
私はこれを聴くとベースが弾きたくなる。
そして後半の長いギター・ソロも聴き所満載だ。
そして7曲目「剣を捨てろ」。
アルバムのラストを飾るに相応しい、壮大で感動的な曲。
後半のツイン・ギターがハモッてるようで、微妙に違うフレーズを弾いているのだが、異なるメロディを同時に演奏して一つの音楽にするっていのは、構想としては他にもあったと思うが、ここまで完成させている例は珍しいと思う。
| 名盤100選へ戻る |
ノーメイク時代のキッスを支えたミュージシャンたち
第1回ヴィニー・ヴィンセントと「リック・イット・アップ」

ここでのギタリストはヴィニー・ヴィンセントだ。
彼はすでに前作「クリーチャーズ・オブ・ザ・ナイト」の大半でギターを弾いており、曲作りもしている。
彼はギターの腕前、作曲力など相当な実力を持っているにもかかわらず、ジーン・シモンズとポール・スタンレーから嫌われて、このアルバム製作後、とりあえずツアーだけはこなすのだが、その後バンドを辞めている。
ギター・スタイルとしては、硬質な音色で、マシンガン・ピッキングによる速弾きと、派手なチョーキング、チョーキング+アームが印象的な80年代的ギタリストだ。

彼がジーンとポールという大御所2人に嫌われた原因としては、オリジナルメンバーであるエース・フレイリーのフレーズを弾かない、新入りなのに意見が多い、それとギャラの問題だと言われている。
しかし、アルバム製作において才能を発揮していることには変わりなく、彼の直接かかわった2枚のアルバムの出来は素晴らしいものだ。
このアルバムは、全体的にハードでメタリックな印象がある。
メイク時代のアルバム「ダイナスティ」以降、ポップ路線に走ったり、コンセプト・アルバム「エルダー」を作ったりと迷っていた時期があったが、前作からのメタル路線に落ち着いたようだ。
おそらく、イギリスで巻き起こったニュー・ウェイブ・オブ・ブリティッシュ・ヘヴィ・メタル(NWOBHM)の影響だろう。
それがとくに顕著に現れているのが、4曲目「ヤング・アンド・ウェイステッド」や5曲目「ギミー・モア」、8曲目「フィッツ・ライク・ア・グルーヴ」といったハードナンバーだろう。
これらの曲は、70年代のKISSにはなかったタイプだ。
こういった路線を可能にしたのが、やはり新しく加入したドラムのエリック・カーとヴィニーの力が大きいと思う。
とくに「ヤング~」は、リフといい、重いけどグルーヴ感溢れるリズムといい、この時期のKISSを代表する曲だ。
ライブでは、エリック・カーのハスキー・ボーカルがカッコイイ曲でもある(アルバム・ヴァージョンはジーンのボーカル)。
またこの曲のギターは、ヴィニーの硬質なプレイの良さが発揮されている。
それら以外の曲では、ポールの活躍が目立っているように感じる。
1曲目「エキサイター」はポールらしい、メロディアスでハードな曲。
当時のライブのセットリストにあまり入ってないのは何故だろう。
それと7曲目「ア・ミリオン・トゥ・ワン」。
哀愁のメロディ、バックで流れるアルペジオ、まさに隠れた名曲だ。
自身のソロツアーでは、この曲をやってるようだが、是非キッスとしてもやってもらいたい。
カテゴリー一覧
ホーム
第1回ヴィニー・ヴィンセントと「リック・イット・アップ」
ここでのギタリストはヴィニー・ヴィンセントだ。
彼はすでに前作「クリーチャーズ・オブ・ザ・ナイト」の大半でギターを弾いており、曲作りもしている。
彼はギターの腕前、作曲力など相当な実力を持っているにもかかわらず、ジーン・シモンズとポール・スタンレーから嫌われて、このアルバム製作後、とりあえずツアーだけはこなすのだが、その後バンドを辞めている。
ギター・スタイルとしては、硬質な音色で、マシンガン・ピッキングによる速弾きと、派手なチョーキング、チョーキング+アームが印象的な80年代的ギタリストだ。
彼がジーンとポールという大御所2人に嫌われた原因としては、オリジナルメンバーであるエース・フレイリーのフレーズを弾かない、新入りなのに意見が多い、それとギャラの問題だと言われている。
しかし、アルバム製作において才能を発揮していることには変わりなく、彼の直接かかわった2枚のアルバムの出来は素晴らしいものだ。
このアルバムは、全体的にハードでメタリックな印象がある。
メイク時代のアルバム「ダイナスティ」以降、ポップ路線に走ったり、コンセプト・アルバム「エルダー」を作ったりと迷っていた時期があったが、前作からのメタル路線に落ち着いたようだ。
おそらく、イギリスで巻き起こったニュー・ウェイブ・オブ・ブリティッシュ・ヘヴィ・メタル(NWOBHM)の影響だろう。
それがとくに顕著に現れているのが、4曲目「ヤング・アンド・ウェイステッド」や5曲目「ギミー・モア」、8曲目「フィッツ・ライク・ア・グルーヴ」といったハードナンバーだろう。
これらの曲は、70年代のKISSにはなかったタイプだ。
こういった路線を可能にしたのが、やはり新しく加入したドラムのエリック・カーとヴィニーの力が大きいと思う。
とくに「ヤング~」は、リフといい、重いけどグルーヴ感溢れるリズムといい、この時期のKISSを代表する曲だ。
ライブでは、エリック・カーのハスキー・ボーカルがカッコイイ曲でもある(アルバム・ヴァージョンはジーンのボーカル)。
またこの曲のギターは、ヴィニーの硬質なプレイの良さが発揮されている。
それら以外の曲では、ポールの活躍が目立っているように感じる。
1曲目「エキサイター」はポールらしい、メロディアスでハードな曲。
当時のライブのセットリストにあまり入ってないのは何故だろう。
それと7曲目「ア・ミリオン・トゥ・ワン」。
哀愁のメロディ、バックで流れるアルペジオ、まさに隠れた名曲だ。
自身のソロツアーでは、この曲をやってるようだが、是非キッスとしてもやってもらいたい。
カテゴリー一覧
ホーム
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
[02/26 take surveys for money]
[02/03 Ahapenij]
[12/18 Blealgagors]
[12/17 BisiomoLofs]
[12/16 Looporwaply]
最新記事
(07/20)
(10/21)
(10/20)
(10/14)
(10/13)
最新TB
プロフィール
HN:
にゅーめん
性別:
男性
趣味:
音楽 読書
自己紹介:
音楽を愛する中年男の叫び
ブログ内検索
忍者アナライズ
