洋楽名盤紹介と日々の雑談を書いてます
第34回名盤シリーズ
今回は70年代初頭のグラムロック、T.レックス「電気の武者」だ。
(1971年作品)
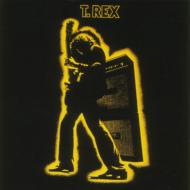
私は長い間グラムロックは苦手だった。
今も得意ではないが、以前よりはかなり理解出来るようになったとは思う。
やはり、年月を経てジックリと聴いてみるとジワジワ良さもわかってくることもあるのだ。
今回この記事を書くにあたり、何度も聴きなおしてみてわかったのは、この気だるい雰囲気に身を任せて聴いてほうがいいってこと。
ゆったりとしたリズム、決して慌てず騒がず。
そうすると、マーク・ボランのボーカルも心地よく聴こえてくるから不思議だ。
そういった特徴がとくに現れているのが、4曲目「Monolith」。
ずっと一定のリズムで緊張感の欠片もない。
しかしメロディがよいのと、ダランとしているけど盛り上がる部分はそれなりに盛り上がり、聞くものを飽きさせない。
合間にはいるワウギターがいい味を出し、ボランの気だるいボーカルも雰囲気がある。
そしてポップな「Bang a Gong(Get It On)」。
80年代にデュラン・デュランのメンバーらが結成したバンド(何という名前か忘れた)がカバーした。
ロックンロール風のギター・リフにカッティングが絡んできて、軽快なリズムで曲は進行する。
サビは覚え易く、1回聴けば皆で口ずさめる。
こういう親しみ易さも、T.レックスの人気の秘訣かもしれない。
ちょっぴりせつないバラード「Girl」。
アコギの弾き語り調の曲で、ホルンみたいな音がホノボノした雰囲気を醸し出している。
「Life's a Gas」は短いけど、味わい深く、つい何度も聴いてしまう曲だ。
ちょっと不思議なメロディ、変な音の短いギターソロ、変わってるけど好きな曲だ。
今回は70年代初頭のグラムロック、T.レックス「電気の武者」だ。
(1971年作品)
私は長い間グラムロックは苦手だった。
今も得意ではないが、以前よりはかなり理解出来るようになったとは思う。
やはり、年月を経てジックリと聴いてみるとジワジワ良さもわかってくることもあるのだ。
今回この記事を書くにあたり、何度も聴きなおしてみてわかったのは、この気だるい雰囲気に身を任せて聴いてほうがいいってこと。
ゆったりとしたリズム、決して慌てず騒がず。
そうすると、マーク・ボランのボーカルも心地よく聴こえてくるから不思議だ。
そういった特徴がとくに現れているのが、4曲目「Monolith」。
ずっと一定のリズムで緊張感の欠片もない。
しかしメロディがよいのと、ダランとしているけど盛り上がる部分はそれなりに盛り上がり、聞くものを飽きさせない。
合間にはいるワウギターがいい味を出し、ボランの気だるいボーカルも雰囲気がある。
そしてポップな「Bang a Gong(Get It On)」。
80年代にデュラン・デュランのメンバーらが結成したバンド(何という名前か忘れた)がカバーした。
ロックンロール風のギター・リフにカッティングが絡んできて、軽快なリズムで曲は進行する。
サビは覚え易く、1回聴けば皆で口ずさめる。
こういう親しみ易さも、T.レックスの人気の秘訣かもしれない。
ちょっぴりせつないバラード「Girl」。
アコギの弾き語り調の曲で、ホルンみたいな音がホノボノした雰囲気を醸し出している。
「Life's a Gas」は短いけど、味わい深く、つい何度も聴いてしまう曲だ。
ちょっと不思議なメロディ、変な音の短いギターソロ、変わってるけど好きな曲だ。
| 名盤100選へ戻る |
PR
第33回名盤シリーズ
今回はヘヴィメタ界のカリスマ・ボーカリスト、オジー・オズボーンのソロ1作目「ブリザード・オブ・オズ」。
(1980年作品)

ブラック・サバス脱退後のオジー・オズボーンのソロ・プロジェクトである。
このアルバムには、サバス時代のオドロオドロしさと80年代的華やかさがうまくミックスされている。
やはり注目すべきはランディ・ローズのギター・ワークだろう。
そのリフ構成は完全に80年代以降の音で、発売当時新しい時代の幕開けを予感させるものだった。
それまでのトニー・アイオミやジミー・ペイジなどの名リフ・メイカーとは全く違う手法で、巧みに16部の低音弦刻みを織り交ぜた当時としては斬新なものだった。
とくにそれは顕著に現れているのが、1曲目「アイ・ドント・ノー」や続く「クレイジー・トレイン」だ。
非常にスピード感があり、重さもあるリフ構成は、今聴いても古さを感じさせない。
そしてなんと言っても華麗なギター・ソロだ。
よく練られた美しいコード進行をベースに、クラシカルで美しく、しかもスリリングで緊張感あふれるギター・ソロを展開するのだ。
とくに名曲の誉れ高い「ミスター・クロウリー」と「レヴェレーション」。
このコード進行にはこのメロディしかありえないのでは?と思うほど完成されたギター・ソロである。
「ミスター・クロウリー」の後半のギター・ソロなんて完璧なソロの一つだろう。
高速アルペジオでスタート→トリルを効果的に用いたメロディアス・パート→ハンマリングで下から駆け上がり→トリルでさらに上昇→フルピッキングで一気に駆け下りる→フェイドアウト、と全く非の打ち所のないものだ。
また適度なポップ感もこのアルバムの特徴である。
すでに70年代後半のサバスのアルバムには、ポップテイストの曲があったのはあったが、ここまで華やかなムードはなかった。
前述の「クレイジー・トレイン」は今もライブでの重要なレパートリーとなっているが、このポップ性が今も人気の秘訣だろう。
ランディが残した音源はあまりにも少なく、スタジオ・アルバムはこれと次の「ダイアリー・オブ・ア・マッドマン」だけである。
あまりにも早すぎる死ゆえに、すでに伝説となっているが、彼が生きていたら相当なギタリストに成長していたことだろう。
なぜなら、生前残したアルバムでのギター・ワークはこれほどの完成度を持ちながらも、まだ「未完成感」があるからだ。
今回はヘヴィメタ界のカリスマ・ボーカリスト、オジー・オズボーンのソロ1作目「ブリザード・オブ・オズ」。
(1980年作品)
ブラック・サバス脱退後のオジー・オズボーンのソロ・プロジェクトである。
このアルバムには、サバス時代のオドロオドロしさと80年代的華やかさがうまくミックスされている。
やはり注目すべきはランディ・ローズのギター・ワークだろう。
そのリフ構成は完全に80年代以降の音で、発売当時新しい時代の幕開けを予感させるものだった。
それまでのトニー・アイオミやジミー・ペイジなどの名リフ・メイカーとは全く違う手法で、巧みに16部の低音弦刻みを織り交ぜた当時としては斬新なものだった。
とくにそれは顕著に現れているのが、1曲目「アイ・ドント・ノー」や続く「クレイジー・トレイン」だ。
非常にスピード感があり、重さもあるリフ構成は、今聴いても古さを感じさせない。
そしてなんと言っても華麗なギター・ソロだ。
よく練られた美しいコード進行をベースに、クラシカルで美しく、しかもスリリングで緊張感あふれるギター・ソロを展開するのだ。
とくに名曲の誉れ高い「ミスター・クロウリー」と「レヴェレーション」。
このコード進行にはこのメロディしかありえないのでは?と思うほど完成されたギター・ソロである。
「ミスター・クロウリー」の後半のギター・ソロなんて完璧なソロの一つだろう。
高速アルペジオでスタート→トリルを効果的に用いたメロディアス・パート→ハンマリングで下から駆け上がり→トリルでさらに上昇→フルピッキングで一気に駆け下りる→フェイドアウト、と全く非の打ち所のないものだ。
また適度なポップ感もこのアルバムの特徴である。
すでに70年代後半のサバスのアルバムには、ポップテイストの曲があったのはあったが、ここまで華やかなムードはなかった。
前述の「クレイジー・トレイン」は今もライブでの重要なレパートリーとなっているが、このポップ性が今も人気の秘訣だろう。
ランディが残した音源はあまりにも少なく、スタジオ・アルバムはこれと次の「ダイアリー・オブ・ア・マッドマン」だけである。
あまりにも早すぎる死ゆえに、すでに伝説となっているが、彼が生きていたら相当なギタリストに成長していたことだろう。
なぜなら、生前残したアルバムでのギター・ワークはこれほどの完成度を持ちながらも、まだ「未完成感」があるからだ。
| 名盤100選へ戻る |
第32回名盤シリーズ
今回取り上げるのはクラッシュ「パールハーバー79」
(1979年作品)
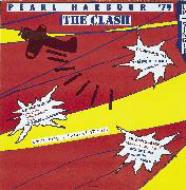
普通、クラッシュといえば「白い暴動」や「ロンドン・コーリング」だと思うが、あえてこの日本企画盤を選んだ。
「ロンドン・コーリング」は人気のアルバムだが、パンク色は薄れ「アメリカ人でも聴くパンク」などと呼ばれるロックンロール色の濃いアルバムだった。
で、よりクラッシュらしい、よりパンクらしいのは「白い暴動」のほう。
しかし私はどうしても「クラッシュ・シティ・ロッカーズ」や「アイ・フォート・ザ・ロウ」の入ってるアルバムにしたかったので、このアルバムを選んだのだった。
この日本限定企画盤はアルバム「白い暴動」US盤全曲にシングル曲の「クラッシュ・シティ・ロッカーズ」「アイ・フォート・ザ・ロウ」など数曲を加えたものだ。
今の感覚でいえば、ボーナストラックが入ってるような感じだろう。
メンバーは、ジョー・ストラマー(vo、g)、ミック・ジョーンズ(vo、g)、ポール・シムノン(b)、テリー・チャイムス(ds)
サウンドは荒々しいロックンロール。
歌詞は反米を主体としていて、2曲目に「反米愛国」という曲が入っている。
当時のツアー名が、このアルバムタイトルになった「パール・ハーバー79」という反米感情むき出しで、アルバムジャケットはゼロ戦が爆弾を落としてるもの。
ここまでやるか?と思ってしまうほどだ。
アルバムは当時のライブのオープニングである「クラッシュ・シティ・ロッカーズ」から。
かっこいいロックンロールだ。
特にサビになって定型リズムになり、コーラスが入る部分のノリがよくっていい。
このアルバムはメンバー自信が選曲しているのだが、ライブの構成と同じになっているのが、他のアルバムと違うところだ。
当時来日のなかったクラッシュだが、日本のファンはこれを聴いてライブを想像したことだろう。
続く「反米愛国」はセックス・ピストルズっぽい曲。
この曲の出だしで「ヤンキー、ソールジャー~」と歌うところが微笑ましい。
またピストルズと違って親しみやすくメロディアスなところがいい。
そのメロディアスな面がよく表れているのが「コンプリート・コントロール」や「出世のチャンス」、「ポリスとコソ泥」あたり。
非常にポップでもある。
また積極的にレゲエのリズムなども取り入れる柔軟なところもクラッシュらしいところだ。
「ハマー・スミスの宮殿」でそれを聴くことが出来る。
このアルバムで最も有名なのはやはり「アイ・フォート・ザ・ロウ」だ。
少し前にもテレビCMでも使われていたので知ってる人も多いと思うが(クラッシュ・バージョンじゃなかったが)
メロディアスでポップでわかりやすいメロディ、クラッシュらしい曲である。
日本のモッズなどは思いっきり影響を受けているようだ。
この親しみ易さが多くの支持を受ける最大の理由であることは間違いない。
今回取り上げるのはクラッシュ「パールハーバー79」
(1979年作品)
普通、クラッシュといえば「白い暴動」や「ロンドン・コーリング」だと思うが、あえてこの日本企画盤を選んだ。
「ロンドン・コーリング」は人気のアルバムだが、パンク色は薄れ「アメリカ人でも聴くパンク」などと呼ばれるロックンロール色の濃いアルバムだった。
で、よりクラッシュらしい、よりパンクらしいのは「白い暴動」のほう。
しかし私はどうしても「クラッシュ・シティ・ロッカーズ」や「アイ・フォート・ザ・ロウ」の入ってるアルバムにしたかったので、このアルバムを選んだのだった。
この日本限定企画盤はアルバム「白い暴動」US盤全曲にシングル曲の「クラッシュ・シティ・ロッカーズ」「アイ・フォート・ザ・ロウ」など数曲を加えたものだ。
今の感覚でいえば、ボーナストラックが入ってるような感じだろう。
メンバーは、ジョー・ストラマー(vo、g)、ミック・ジョーンズ(vo、g)、ポール・シムノン(b)、テリー・チャイムス(ds)
サウンドは荒々しいロックンロール。
歌詞は反米を主体としていて、2曲目に「反米愛国」という曲が入っている。
当時のツアー名が、このアルバムタイトルになった「パール・ハーバー79」という反米感情むき出しで、アルバムジャケットはゼロ戦が爆弾を落としてるもの。
ここまでやるか?と思ってしまうほどだ。
アルバムは当時のライブのオープニングである「クラッシュ・シティ・ロッカーズ」から。
かっこいいロックンロールだ。
特にサビになって定型リズムになり、コーラスが入る部分のノリがよくっていい。
このアルバムはメンバー自信が選曲しているのだが、ライブの構成と同じになっているのが、他のアルバムと違うところだ。
当時来日のなかったクラッシュだが、日本のファンはこれを聴いてライブを想像したことだろう。
続く「反米愛国」はセックス・ピストルズっぽい曲。
この曲の出だしで「ヤンキー、ソールジャー~」と歌うところが微笑ましい。
またピストルズと違って親しみやすくメロディアスなところがいい。
そのメロディアスな面がよく表れているのが「コンプリート・コントロール」や「出世のチャンス」、「ポリスとコソ泥」あたり。
非常にポップでもある。
また積極的にレゲエのリズムなども取り入れる柔軟なところもクラッシュらしいところだ。
「ハマー・スミスの宮殿」でそれを聴くことが出来る。
このアルバムで最も有名なのはやはり「アイ・フォート・ザ・ロウ」だ。
少し前にもテレビCMでも使われていたので知ってる人も多いと思うが(クラッシュ・バージョンじゃなかったが)
メロディアスでポップでわかりやすいメロディ、クラッシュらしい曲である。
日本のモッズなどは思いっきり影響を受けているようだ。
この親しみ易さが多くの支持を受ける最大の理由であることは間違いない。
| 名盤100選へ戻る |
第31回名盤シリーズ
ホワイト・スネイクが苦労して作り上げた作品「スライド・イット・イン」
(1983年作品)
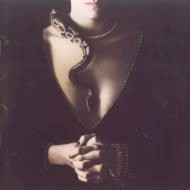
10代半ば頃、ホワイトスネイクはベスト盤を聴いて、それまでの代表曲はだいたい聴いていた。
そして、次のニューアルバムの製作は難航しているとの情報がミュージック・ライフ誌に報じられていた。
いろいろな人間関係の問題などが山積みらしい。
その後発売されたこのアルバム、発売と同時に聴いたのだが、かなり気に入ったアルバムで、それが今回紹介する「スライド・イット・イン」だ。
このアルバムには、古き良きホワイトスネイクの味わいが残っている。
次の「サーペンス・アルバス」のようなキャッチーで売れ線な曲はなく、初期ホワイトスネイクが持っていたブルージーで泥臭い雰囲気が残ってるのだ。
ツインギターバンドでありながら、あくまでもデビッド・カバーデイルのボーカルを引き立てるためのもの。
同時期のLAメタルとはまるで違うサウンドで、ブリティッシュ・ロック臭さが漂う大人のハード・ロック。
ギターはミッキー・ムーディーとメル・ギャレーという渋いメンバーなのだが、私はホワイトスネイクにスーパーギタリストは必要ないと思う。
いや、ミッキーもメルも上手さに関しては折り紙付きなのだが。
派手なジョン・サイクスや後のヴィヴィアン・キャンベル、エイドリアン・ヴァンデンヴァーグ、スティーヴ・ヴァイなど、スター性のあるギタリストを迎えた作品は、成功を手にした代わりに失ったものも多いと思う。
1曲目の「ギャンブラー」、名作を予感させるかっこいいスタートだ。
渋カッコイイ曲で、控えめなギター・ソロもいい。
このアルバムでもう1曲一押しは、「孤独の影」。
地味だが、役割分担のはっきりしたツインギターに、これまたソウルフルなカバーデイルのボーカル。
ギターの音がハードロック然としていないのも、このアルバムらしくていい。
間奏のギターソロも必要最小限の音数で、80年代ギターテクニカル競争の時代に珍しいくらい味で勝負のプレイだ。
その後の渋すぎるボーカルも大人っぽくて好きだった。
その後、アメリカ向けにミックスされたバージョンが発売される。
ギターがジョン・サイクスに差し替えられ、このブリティッシュな雰囲気は封印されてしまうのだった。
ホワイト・スネイクが苦労して作り上げた作品「スライド・イット・イン」
(1983年作品)
10代半ば頃、ホワイトスネイクはベスト盤を聴いて、それまでの代表曲はだいたい聴いていた。
そして、次のニューアルバムの製作は難航しているとの情報がミュージック・ライフ誌に報じられていた。
いろいろな人間関係の問題などが山積みらしい。
その後発売されたこのアルバム、発売と同時に聴いたのだが、かなり気に入ったアルバムで、それが今回紹介する「スライド・イット・イン」だ。
このアルバムには、古き良きホワイトスネイクの味わいが残っている。
次の「サーペンス・アルバス」のようなキャッチーで売れ線な曲はなく、初期ホワイトスネイクが持っていたブルージーで泥臭い雰囲気が残ってるのだ。
ツインギターバンドでありながら、あくまでもデビッド・カバーデイルのボーカルを引き立てるためのもの。
同時期のLAメタルとはまるで違うサウンドで、ブリティッシュ・ロック臭さが漂う大人のハード・ロック。
ギターはミッキー・ムーディーとメル・ギャレーという渋いメンバーなのだが、私はホワイトスネイクにスーパーギタリストは必要ないと思う。
いや、ミッキーもメルも上手さに関しては折り紙付きなのだが。
派手なジョン・サイクスや後のヴィヴィアン・キャンベル、エイドリアン・ヴァンデンヴァーグ、スティーヴ・ヴァイなど、スター性のあるギタリストを迎えた作品は、成功を手にした代わりに失ったものも多いと思う。
1曲目の「ギャンブラー」、名作を予感させるかっこいいスタートだ。
渋カッコイイ曲で、控えめなギター・ソロもいい。
このアルバムでもう1曲一押しは、「孤独の影」。
地味だが、役割分担のはっきりしたツインギターに、これまたソウルフルなカバーデイルのボーカル。
ギターの音がハードロック然としていないのも、このアルバムらしくていい。
間奏のギターソロも必要最小限の音数で、80年代ギターテクニカル競争の時代に珍しいくらい味で勝負のプレイだ。
その後の渋すぎるボーカルも大人っぽくて好きだった。
その後、アメリカ向けにミックスされたバージョンが発売される。
ギターがジョン・サイクスに差し替えられ、このブリティッシュな雰囲気は封印されてしまうのだった。
| 名盤100選へ戻る |
第30回名盤シリーズ
今回取り上げるのはギター革命児ジミヘンの「エレクトリック・レディ・ランド」である。
(1968年作品)
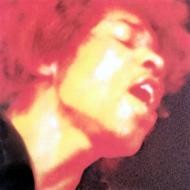
私はまだまだジミヘンを理解しているとは言いがたく、今も取っ付き難い人である。
ギタリストの間で、ジミヘンは大変評価が高く、神の域にまで達している感があるが、自分自身ギターを弾くにもかかわらず、理解が難しいのだ。
私が初めて買ったジミヘンは、彼の死後に発売された「クライ・オブ・ラブ」というアルバム。
何でこのアルバムかっていうと、行き着けのレコード屋さんにこれしかなかったからだ。
そして、物凄いギタープレイを期待して聴いたのだが、思いっきり肩透かしを食らった。
じっくり聴くと曲の質はいいのだが、自分には大人しすぎるアルバムだったからである。
でもこのアルバムは違う。
1968年に2枚組LPとして発表された本作は、しっかり素晴らしいギター・プレイが満載で聴き応えたっぷりだ。
曲も良く、彼のソングライターとしての力も発揮されている。
なかでも「Burning of the Midnight Lamp 」はメロディメーカーとしても、優れたものを持っていたことがよくわかる曲だと思う。
また「1983…」の予想のつかない展開はプログレ的で、中間部の混沌とした感じはまるでアイランド期のクリムゾンみたいだ。
渋いギターを楽しむならこの曲、「Voodoo Chile」だ。
それも有名なスライトリターンじゃなく、4曲目のスローブルースのほう。
ブルースマンとしてのジミの実力が発揮された曲だと思う。
ヘヴィなリズムをバックに決して音数が多いわけではないのに、激しくエモーショナルなギターを聴かせてくれる。
ここで聴けるギターは彼の魂そのもののような気がするのだ。
絶妙なチョーキングビブラートとトリルを絡ませたギターを聴いて「これがジミヘンのギターか!」と納得した。
攻撃的なギターを聴くなら「Voodoo Chile」のスライトリターンのほう。
暴力的ともいえる凄まじいソロが聴けるが、途中の副音をトレモロピッキングでかき鳴らすところはスゴイの一言だ。
残念ながらもっと聴きたいのにスタジオバージョンはすぐにフェイドアウトしてしまう。
その分ライブだと10分くらいソロを弾いてくれるのだが。
また、ソロだけでなくリフメイカーとしても個性的なジミヘン。
2曲目「Have You Ever Been 」で聴けるコードにトリルを絡ませるリフや、「Crosstown Traffic」でのコードと単音を組み合わせたリフなどジミヘンのリフ構成の特徴が現れている。
そしてもう一つの重要な特徴であるワウを効かせたリフ。
これは「Voodoo Chile」のスライトリターンのほうで聴くことが出来る。
ここで聴けるボーカルメロディとリフを同期させるパターンもジミヘン独自のものだ。
後に多くのギタリスト、いや全てのギタリストに大きな影響を与えたジミヘン。
短い活動期間中に思いっきり才能を凝縮させて早死するが、彼の残した遺産は永遠の輝きを放つことだろう。
今回取り上げるのはギター革命児ジミヘンの「エレクトリック・レディ・ランド」である。
(1968年作品)
私はまだまだジミヘンを理解しているとは言いがたく、今も取っ付き難い人である。
ギタリストの間で、ジミヘンは大変評価が高く、神の域にまで達している感があるが、自分自身ギターを弾くにもかかわらず、理解が難しいのだ。
私が初めて買ったジミヘンは、彼の死後に発売された「クライ・オブ・ラブ」というアルバム。
何でこのアルバムかっていうと、行き着けのレコード屋さんにこれしかなかったからだ。
そして、物凄いギタープレイを期待して聴いたのだが、思いっきり肩透かしを食らった。
じっくり聴くと曲の質はいいのだが、自分には大人しすぎるアルバムだったからである。
でもこのアルバムは違う。
1968年に2枚組LPとして発表された本作は、しっかり素晴らしいギター・プレイが満載で聴き応えたっぷりだ。
曲も良く、彼のソングライターとしての力も発揮されている。
なかでも「Burning of the Midnight Lamp 」はメロディメーカーとしても、優れたものを持っていたことがよくわかる曲だと思う。
また「1983…」の予想のつかない展開はプログレ的で、中間部の混沌とした感じはまるでアイランド期のクリムゾンみたいだ。
渋いギターを楽しむならこの曲、「Voodoo Chile」だ。
それも有名なスライトリターンじゃなく、4曲目のスローブルースのほう。
ブルースマンとしてのジミの実力が発揮された曲だと思う。
ヘヴィなリズムをバックに決して音数が多いわけではないのに、激しくエモーショナルなギターを聴かせてくれる。
ここで聴けるギターは彼の魂そのもののような気がするのだ。
絶妙なチョーキングビブラートとトリルを絡ませたギターを聴いて「これがジミヘンのギターか!」と納得した。
攻撃的なギターを聴くなら「Voodoo Chile」のスライトリターンのほう。
暴力的ともいえる凄まじいソロが聴けるが、途中の副音をトレモロピッキングでかき鳴らすところはスゴイの一言だ。
残念ながらもっと聴きたいのにスタジオバージョンはすぐにフェイドアウトしてしまう。
その分ライブだと10分くらいソロを弾いてくれるのだが。
また、ソロだけでなくリフメイカーとしても個性的なジミヘン。
2曲目「Have You Ever Been 」で聴けるコードにトリルを絡ませるリフや、「Crosstown Traffic」でのコードと単音を組み合わせたリフなどジミヘンのリフ構成の特徴が現れている。
そしてもう一つの重要な特徴であるワウを効かせたリフ。
これは「Voodoo Chile」のスライトリターンのほうで聴くことが出来る。
ここで聴けるボーカルメロディとリフを同期させるパターンもジミヘン独自のものだ。
後に多くのギタリスト、いや全てのギタリストに大きな影響を与えたジミヘン。
短い活動期間中に思いっきり才能を凝縮させて早死するが、彼の残した遺産は永遠の輝きを放つことだろう。
| 名盤100選へ戻る |
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
[02/26 take surveys for money]
[02/03 Ahapenij]
[12/18 Blealgagors]
[12/17 BisiomoLofs]
[12/16 Looporwaply]
最新記事
(07/20)
(10/21)
(10/20)
(10/14)
(10/13)
最新TB
プロフィール
HN:
にゅーめん
性別:
男性
趣味:
音楽 読書
自己紹介:
音楽を愛する中年男の叫び
ブログ内検索
忍者アナライズ
