洋楽名盤紹介と日々の雑談を書いてます
第48回名盤シリーズ
ブライアン・セッツァー率いるロカビリー・トリオ、ストレイ・キャッツ「ビルト・フォー・スピード」
(1982年作品)
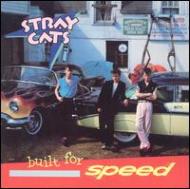
彼らはアメリカのバンドですが、先にイギリスでデビューし、このアルバムはアメリカでのデビュー盤になる。
80年代の50’sブームの中、アメリカや日本でも人気があった。
当時は日本でも不良ルックでロックンロールを演奏するスタイルが人気で、ストレイ・キャッツを受け入れる基盤が出来ていたと言える。
彼らのサウンドは、50’sのオールディーズなロックンロールスタイルをベースに、完全に新しいスタイルとしてのロカビリーを演奏している。
例えば、スリム・ジム・ファントムのドラムス。
バスとスネアだけで、あとはシンバルがあるだけの超シンプルなセットで、それを立って叩くという独自のスタイルだ。
それにリー・ロッカーのウッド・ベース。
実は50’sのロカビリー、ロックンロールシーンではエレキ・ベースが主流だったのだが、彼らはジャズ的なウッドベースを取り入れ、独特のスイング感をだし、後にこの手のスタンダードとなる。
そしてなんといってもブライアンのギタースタイルだ。
クラシカルなセミアコ・ギターをクリア・トーンで弾くのは、50’sスタイルだが、さらにテクニカルに完璧に演奏するのである。
かなり上手い。
その上手さというのは、ヘビメタ・ギタリストのそれではなく、完全にブライアン流のスタイルで、彼にしか弾けない個性に溢れている。
ブライアンのボーカル・スタイルは、エルヴィス・プレスリーの影響が強いように感じる。
いわゆる「低音の魅力」みたいな声で歌うときもあれば、高い声でシャウトをするときもある。
で、ちょっと青臭さの残った部分にヤンチャ坊主的な雰囲気を醸し出し、彼独特のスタイルを作っている。
ネオ・ロカビリーと言われるサウンドを確立した彼らは各国で人気を得るのだが、日本ではちょっとおかしな売られ方がされた。
ターゲット層をヤンキー少年少女(たとえば「横浜銀蝿」あたりのファン)に特定したようで、ダサすぎる邦題がついたりしていた(「ごーいんDOWNTOWN」とか)。
しかし、実際にストレイ・キャッツを聴いていたのは普通の洋楽ファンが中心だったと思う。
曲の大半は元気のいいロカビリー/ロックンロールだが、素敵なバラードもある。
サックスの響きが哀愁を誘う「おもいでサマーナイト」なんかはかなりの名曲だ。
その後彼らの影響を受けたネオロカビリーバンドがいくつかデビューしましたが、今は全く見かけなくなった。
本家本元の彼らは、たまに再結成ライブなども行ってるようだ。
もちろんブライアン・セッツァー・オーケストラは今も現役である。
ブライアン・セッツァー率いるロカビリー・トリオ、ストレイ・キャッツ「ビルト・フォー・スピード」
(1982年作品)
彼らはアメリカのバンドですが、先にイギリスでデビューし、このアルバムはアメリカでのデビュー盤になる。
80年代の50’sブームの中、アメリカや日本でも人気があった。
当時は日本でも不良ルックでロックンロールを演奏するスタイルが人気で、ストレイ・キャッツを受け入れる基盤が出来ていたと言える。
彼らのサウンドは、50’sのオールディーズなロックンロールスタイルをベースに、完全に新しいスタイルとしてのロカビリーを演奏している。
例えば、スリム・ジム・ファントムのドラムス。
バスとスネアだけで、あとはシンバルがあるだけの超シンプルなセットで、それを立って叩くという独自のスタイルだ。
それにリー・ロッカーのウッド・ベース。
実は50’sのロカビリー、ロックンロールシーンではエレキ・ベースが主流だったのだが、彼らはジャズ的なウッドベースを取り入れ、独特のスイング感をだし、後にこの手のスタンダードとなる。
そしてなんといってもブライアンのギタースタイルだ。
クラシカルなセミアコ・ギターをクリア・トーンで弾くのは、50’sスタイルだが、さらにテクニカルに完璧に演奏するのである。
かなり上手い。
その上手さというのは、ヘビメタ・ギタリストのそれではなく、完全にブライアン流のスタイルで、彼にしか弾けない個性に溢れている。
ブライアンのボーカル・スタイルは、エルヴィス・プレスリーの影響が強いように感じる。
いわゆる「低音の魅力」みたいな声で歌うときもあれば、高い声でシャウトをするときもある。
で、ちょっと青臭さの残った部分にヤンチャ坊主的な雰囲気を醸し出し、彼独特のスタイルを作っている。
ネオ・ロカビリーと言われるサウンドを確立した彼らは各国で人気を得るのだが、日本ではちょっとおかしな売られ方がされた。
ターゲット層をヤンキー少年少女(たとえば「横浜銀蝿」あたりのファン)に特定したようで、ダサすぎる邦題がついたりしていた(「ごーいんDOWNTOWN」とか)。
しかし、実際にストレイ・キャッツを聴いていたのは普通の洋楽ファンが中心だったと思う。
曲の大半は元気のいいロカビリー/ロックンロールだが、素敵なバラードもある。
サックスの響きが哀愁を誘う「おもいでサマーナイト」なんかはかなりの名曲だ。
その後彼らの影響を受けたネオロカビリーバンドがいくつかデビューしましたが、今は全く見かけなくなった。
本家本元の彼らは、たまに再結成ライブなども行ってるようだ。
もちろんブライアン・セッツァー・オーケストラは今も現役である。
| 名盤100選へ戻る |
PR
第47回名盤シリーズ
今回ドイツのハード・ロック・バンド、スコーピオンズ「ヴァージン・キラー」
(1976年作品)
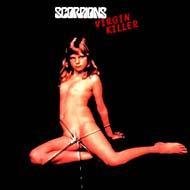
この過激なアルバム・ジャケットはある意味スコーピオンズらしいともいえるもので、国によっては違うジャケになっている。
当時のリード・ギタリストはウリ・ジョン・ロート。
彼のギターのファンは非常に多く、現ギタリストのマティアス・ヤプスよりも人気が高いのではないだろうか?
いわゆるカリスマ・ギタリストで、同じく元スコーピオンズのマイケル・シェンカーと人気を二分する。
彼のギタープレイの特徴は、トリルの多用と情熱的とも言えるチョーキング・ビブラートだ。
このアルバムで聴ける楽曲の数々は、良い意味で暗いサウンドで、音質も湿ったような暗さを伴っている。
1曲目から、派手だがマイナーな曲調によるハード・ロックだ。
この曲では名リフ・メイカー、ルドルフ・シェンカーのギターが光る。
このアルバムを代表する名曲で、私が初めて聴いたスコーピオンズの曲だった。
このアルバムにはバラードが3曲、ハード・ロック・バンドのアルバムとしては異例といえる。
彼らのアルバムには必ずこういった情熱的なバラードが収録されており、暗く悲しいメロディ・ラインは日本人の心に響く類のものだ。
私はこの中でも「In Your Park」と「Crying Days」がとくに素晴らしいと思う。
どちらもウリの泣きのギターが素晴らしく、そのフレーズに「心」を感じさせる。
これについて、なぜそのように感じるのかをずっと考えていたのだが、とりあえず要素が2つ。
1つはフレーズを構成するスケール。
メロディ・ラインがよくあるペンタトニック・スケールばかりではなく、メジャー・スケールも使用している。
これはランディ・ローズなどもそうで、ロック的なカッコよさが少なくなるかわりに、メロディアスなフレーズを作るのに適しているのだろう。
マイケルやマティアスがペンタトニック中心なのに対して、ウリの個性と言える。
もう1つが、チョーキングとビブラートの入れるタイミングだ。
チョーク・アップをした直後からビブラートを始めることもあれば、チョーク・アップしたままタメてからゆったりと震わせたりなど、自在にこれを操っているのである。
それとこの枯れた音色だ。
実に味わい深く、どうやったらこんな音が出るのか不思議である。
ウリのことばかり書いてしまったが、クラウスの艶のある力強いハイトーンボイスの魅力も重要だ。
彼のメロディセンスは日本人の美意識と通じる部分があるようで、「演歌的」な部分があると思う。
今回ドイツのハード・ロック・バンド、スコーピオンズ「ヴァージン・キラー」
(1976年作品)
この過激なアルバム・ジャケットはある意味スコーピオンズらしいともいえるもので、国によっては違うジャケになっている。
当時のリード・ギタリストはウリ・ジョン・ロート。
彼のギターのファンは非常に多く、現ギタリストのマティアス・ヤプスよりも人気が高いのではないだろうか?
いわゆるカリスマ・ギタリストで、同じく元スコーピオンズのマイケル・シェンカーと人気を二分する。
彼のギタープレイの特徴は、トリルの多用と情熱的とも言えるチョーキング・ビブラートだ。
このアルバムで聴ける楽曲の数々は、良い意味で暗いサウンドで、音質も湿ったような暗さを伴っている。
1曲目から、派手だがマイナーな曲調によるハード・ロックだ。
この曲では名リフ・メイカー、ルドルフ・シェンカーのギターが光る。
このアルバムを代表する名曲で、私が初めて聴いたスコーピオンズの曲だった。
このアルバムにはバラードが3曲、ハード・ロック・バンドのアルバムとしては異例といえる。
彼らのアルバムには必ずこういった情熱的なバラードが収録されており、暗く悲しいメロディ・ラインは日本人の心に響く類のものだ。
私はこの中でも「In Your Park」と「Crying Days」がとくに素晴らしいと思う。
どちらもウリの泣きのギターが素晴らしく、そのフレーズに「心」を感じさせる。
これについて、なぜそのように感じるのかをずっと考えていたのだが、とりあえず要素が2つ。
1つはフレーズを構成するスケール。
メロディ・ラインがよくあるペンタトニック・スケールばかりではなく、メジャー・スケールも使用している。
これはランディ・ローズなどもそうで、ロック的なカッコよさが少なくなるかわりに、メロディアスなフレーズを作るのに適しているのだろう。
マイケルやマティアスがペンタトニック中心なのに対して、ウリの個性と言える。
もう1つが、チョーキングとビブラートの入れるタイミングだ。
チョーク・アップをした直後からビブラートを始めることもあれば、チョーク・アップしたままタメてからゆったりと震わせたりなど、自在にこれを操っているのである。
それとこの枯れた音色だ。
実に味わい深く、どうやったらこんな音が出るのか不思議である。
ウリのことばかり書いてしまったが、クラウスの艶のある力強いハイトーンボイスの魅力も重要だ。
彼のメロディセンスは日本人の美意識と通じる部分があるようで、「演歌的」な部分があると思う。
| 名盤100選へ戻る |
第46回名盤シリーズ
今回はビッグブラザー&ホールディングカンパニーのライブ・アルバムだ。
(1968年作品)
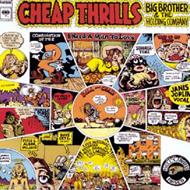
もちろん主役はボーカルのジャニス・ジョプリンなのだが、この荒っぽい演奏によるバックがあってこその名ライブだと思う。
はっきり言って洗練とはほど遠い、口の悪い評論家には「素人に毛がはえた程度」と酷評されるバンドで、ジャニスの実力に伴わないなどと言われる。
しかしここで聴ける演奏は、「良い意味での荒さ」になっていて、かえって迫力が増す結果になってると思うのは私だけだろうか?
曲はブルースをベースにしたロックで、テンポのよいノリのある曲から、スロー・ブルースまでけっこう器用にこなしている。
ギタリストは二人いて、曲によってギター・ソロを弾き分けていますが、ハモったりはしない。
一人は繊細な感じのギターを弾いていて(サマー・タイムのソロを弾いてる方)、もう一人の方が多くリードギターを弾いている。
このもう一人のギタリストは、とにかく豪快なソロを弾く人で、少々のミスとかは気にせず、勢いで弾ききっているような感じだ。
ライブはバンドを紹介するMCからスタートする。
すぐにノリのいいリズムで曲がスタートし、楽しく歌い演奏してる様が眼に浮かぶようだ。
ここで聴けるリズム・ギターは、リズム感があってとてもよい。
ギターソロはよく言えばアバンギャルド、悪くいえばデタラメ弾いてるみたいに聴こえるが、これも味の一つだろう。
それらアップテンポの曲も良いのですが、味わい深い演奏、ボーカルが聴けるのはスロー・ブルースのほうだ。
「サマー・タイム」と「ボールとチェーン」の2曲は、このアルバムを代表する名曲、名演、名唱だろう。
ちょっと昔の演歌みたいなギターで始まる叙情的な「サマー・タイム」。
ジャニスの枯れたボーカルが非常に味わい深く、バックのジャズ的なギターと相まって悲痛な心の内面を垣間見るようである。
ここでのギタープレイはとても印象的なフレーズを弾いていて、この曲を魅力的に演出している。
もう1曲、「ボールとチェーン」、こちらはジャニスの熱烈なボーカルが堪能できるヘヴィなブルース。
イントロからカオスのような演奏がスタートし、「サマー・タイム」とは全く違う一面を覗かせる。
ときにやさしく囁くように、ときには壮絶にシャウトするボーカルが痛々しいほどの説得力で表現されるのだ。
バンドも彼女のボーカルを支えるべく、必死な演奏を行っている。
彼らはおそらくドラッグやアルコールに浸りながらツアーを続けていたと思われ、それがジャニスの早死に繋がってるいると思われる。
しかしこの迫力ある演奏は、そういった精神の限界状態でこそありえたのかも知れず、実に皮肉なものだ。
今回はビッグブラザー&ホールディングカンパニーのライブ・アルバムだ。
(1968年作品)
もちろん主役はボーカルのジャニス・ジョプリンなのだが、この荒っぽい演奏によるバックがあってこその名ライブだと思う。
はっきり言って洗練とはほど遠い、口の悪い評論家には「素人に毛がはえた程度」と酷評されるバンドで、ジャニスの実力に伴わないなどと言われる。
しかしここで聴ける演奏は、「良い意味での荒さ」になっていて、かえって迫力が増す結果になってると思うのは私だけだろうか?
曲はブルースをベースにしたロックで、テンポのよいノリのある曲から、スロー・ブルースまでけっこう器用にこなしている。
ギタリストは二人いて、曲によってギター・ソロを弾き分けていますが、ハモったりはしない。
一人は繊細な感じのギターを弾いていて(サマー・タイムのソロを弾いてる方)、もう一人の方が多くリードギターを弾いている。
このもう一人のギタリストは、とにかく豪快なソロを弾く人で、少々のミスとかは気にせず、勢いで弾ききっているような感じだ。
ライブはバンドを紹介するMCからスタートする。
すぐにノリのいいリズムで曲がスタートし、楽しく歌い演奏してる様が眼に浮かぶようだ。
ここで聴けるリズム・ギターは、リズム感があってとてもよい。
ギターソロはよく言えばアバンギャルド、悪くいえばデタラメ弾いてるみたいに聴こえるが、これも味の一つだろう。
それらアップテンポの曲も良いのですが、味わい深い演奏、ボーカルが聴けるのはスロー・ブルースのほうだ。
「サマー・タイム」と「ボールとチェーン」の2曲は、このアルバムを代表する名曲、名演、名唱だろう。
ちょっと昔の演歌みたいなギターで始まる叙情的な「サマー・タイム」。
ジャニスの枯れたボーカルが非常に味わい深く、バックのジャズ的なギターと相まって悲痛な心の内面を垣間見るようである。
ここでのギタープレイはとても印象的なフレーズを弾いていて、この曲を魅力的に演出している。
もう1曲、「ボールとチェーン」、こちらはジャニスの熱烈なボーカルが堪能できるヘヴィなブルース。
イントロからカオスのような演奏がスタートし、「サマー・タイム」とは全く違う一面を覗かせる。
ときにやさしく囁くように、ときには壮絶にシャウトするボーカルが痛々しいほどの説得力で表現されるのだ。
バンドも彼女のボーカルを支えるべく、必死な演奏を行っている。
彼らはおそらくドラッグやアルコールに浸りながらツアーを続けていたと思われ、それがジャニスの早死に繋がってるいると思われる。
しかしこの迫力ある演奏は、そういった精神の限界状態でこそありえたのかも知れず、実に皮肉なものだ。
| 名盤100選へ戻る |
第45回名盤シリーズ
ホール&オーツ「ロックン・ソウル・パート1」
(1983年作品)

今回取り上げるアルバムは彼らのベストアルバム形式なのだが、当時の新曲も入っている。
「ロックン・ソウル」という洒落たネーミングも面白いが、彼らの作り出すサウンドこそセンスの固まりみたいなものだった。
ダリル・ホールとジョン・オーツのポップ・デュオは、80年代に大変人気があって、テレビでもライブ映像を見たことがある。
とくにダリル・ホールがギターを弾いたり、エレキ・ピアノを弾きながら歌う様はとても印象的だった。
このアルバムを聴いたのは、その映像を見た後だったと思うが、ライブで演奏してた曲など聞き覚えがあって楽しく聴いていた。
このLPを買ったのは私の友人だったが、当時私の周りではとても好評で、普段ハードロックなんかを聴いてる人にもウケが良かった。
それだけ普遍性があり、誰からも好まれる作品だったといえよう。
当時はリズム&ブルースとかソウルなんてまるで知らなくて、「ロックとソウルが合体した音楽なんだな」って勝手に思ってた。
曲自体は普通のポップスのように思うが、ダリル・ホールの歌い方がソウルフルなのだ。
1曲目「セイ・イット・イズント・ソー」なんて、よく出来たエレクトロ・ポップだが、ダリルが歌うと本当にソウルフルに聴こえるから不思議だ。
メロディもどこかモータウン・サウンドの影響が見受けられる。
だから「サラ・スマイル」みたいな、曲自体が黒っぽい曲だと、さらに雰囲気倍増で、たしかにこれは売れるはずだ。
このデュオの話をすると、どうしてもダリルの話題ばかりになるが、もう一人の人、ジョンにもスポットを当てよう。
どちらかというと目立たず、脇役的な存在の相方、ジョン・オーツ。
よく、いてもいなくても同じとか、あまりよい評判ではなかった人だが、彼の弾くギターのカッティングはなかなかカッコよく、影ながらいい仕事をしてると思う。
後のダリルのソロを聴いたところ、そこにはホール&オーツのサウンドはなかった。
やはり二人揃ってのホール&オーツ、ジョンもいなくてはいけない人だったのだ。
この手のポップスは、ロックと違って時代に取り残されていく傾向にあるが、同時代を生きた者の心の中にはいつまでも残っている。
アルバムの最後は「ウェイト・フォー・ミー」のライブ・ヴァージョンで締めくくられる。
感情たっぷりに歌うダリルの歌唱を堪能して、アルバムは終了するのだった。
ホール&オーツ「ロックン・ソウル・パート1」
(1983年作品)
今回取り上げるアルバムは彼らのベストアルバム形式なのだが、当時の新曲も入っている。
「ロックン・ソウル」という洒落たネーミングも面白いが、彼らの作り出すサウンドこそセンスの固まりみたいなものだった。
ダリル・ホールとジョン・オーツのポップ・デュオは、80年代に大変人気があって、テレビでもライブ映像を見たことがある。
とくにダリル・ホールがギターを弾いたり、エレキ・ピアノを弾きながら歌う様はとても印象的だった。
このアルバムを聴いたのは、その映像を見た後だったと思うが、ライブで演奏してた曲など聞き覚えがあって楽しく聴いていた。
このLPを買ったのは私の友人だったが、当時私の周りではとても好評で、普段ハードロックなんかを聴いてる人にもウケが良かった。
それだけ普遍性があり、誰からも好まれる作品だったといえよう。
当時はリズム&ブルースとかソウルなんてまるで知らなくて、「ロックとソウルが合体した音楽なんだな」って勝手に思ってた。
曲自体は普通のポップスのように思うが、ダリル・ホールの歌い方がソウルフルなのだ。
1曲目「セイ・イット・イズント・ソー」なんて、よく出来たエレクトロ・ポップだが、ダリルが歌うと本当にソウルフルに聴こえるから不思議だ。
メロディもどこかモータウン・サウンドの影響が見受けられる。
だから「サラ・スマイル」みたいな、曲自体が黒っぽい曲だと、さらに雰囲気倍増で、たしかにこれは売れるはずだ。
このデュオの話をすると、どうしてもダリルの話題ばかりになるが、もう一人の人、ジョンにもスポットを当てよう。
どちらかというと目立たず、脇役的な存在の相方、ジョン・オーツ。
よく、いてもいなくても同じとか、あまりよい評判ではなかった人だが、彼の弾くギターのカッティングはなかなかカッコよく、影ながらいい仕事をしてると思う。
後のダリルのソロを聴いたところ、そこにはホール&オーツのサウンドはなかった。
やはり二人揃ってのホール&オーツ、ジョンもいなくてはいけない人だったのだ。
この手のポップスは、ロックと違って時代に取り残されていく傾向にあるが、同時代を生きた者の心の中にはいつまでも残っている。
アルバムの最後は「ウェイト・フォー・ミー」のライブ・ヴァージョンで締めくくられる。
感情たっぷりに歌うダリルの歌唱を堪能して、アルバムは終了するのだった。
| 名盤100選へ戻る |
第44回名盤シリーズ
今回取り上げるのはザ・バンド「南十字星」だ。
(1975年作品)

このバンドのサウンドを聴いてアメリカ南部かな?と思ったが、カナダだそうだ。
しかし、そう思ってしまうほど土臭いアメリカンなロックである。
ちょっとカントリーの匂いもする。
彼らの前身はボブ・ディランのバック・バンドだ。
当日の思いつきでセットリストを決定するディランのバックを勤めるには、相当の実力がなければ無理。
50年代末頃から活動をしていた「すでにベテラン・バンド」だった彼らは、そんな無理が通用する実力派だったってことである。
このアルバムを聴いて思うのは「聴き易いアメリカン・ロック」って感じだ。
と言ってもオールマンズみたいなブルースをベースにしてるんじゃなく、どちらかというとカントリーとフォークがベースになってるように思う。
私にはけっこう泥臭いサウンドに聴こえるが、彼らの初期のアルバムに比べると「モダンで都会的」だそうだ。
このアルバムで気に入った曲は1曲目「禁断の木の実」、3曲目「オフェリア」、4曲目「アケイディアの流木」、8曲目「おんぼろ人生」です。
心地よいサウンド、ゆったり流れる時間、大人のロックって感じ。
楽しみながら演奏してる情景が浮かんできそうである。
彼らは実力派中の実力派なので、これくらいの演奏はお手の物で、実に余裕たっぷりだ。
中でも「オフェリア」の楽しそうだが哀愁あるメロディがすごく気に入った。
また、ギター・ソロが実に素晴らしい。
リズミカルで、副音を主体にしたカッティングのようなギター・ソロ。
センスがいいし、なんといっても上手い。
他の曲にも言えることだが、所々でセンスの良さを感じさせるサウンドは、やはりベテラン・バンドの風格みたいなのを感じるのだった。
今回取り上げるのはザ・バンド「南十字星」だ。
(1975年作品)
このバンドのサウンドを聴いてアメリカ南部かな?と思ったが、カナダだそうだ。
しかし、そう思ってしまうほど土臭いアメリカンなロックである。
ちょっとカントリーの匂いもする。
彼らの前身はボブ・ディランのバック・バンドだ。
当日の思いつきでセットリストを決定するディランのバックを勤めるには、相当の実力がなければ無理。
50年代末頃から活動をしていた「すでにベテラン・バンド」だった彼らは、そんな無理が通用する実力派だったってことである。
このアルバムを聴いて思うのは「聴き易いアメリカン・ロック」って感じだ。
と言ってもオールマンズみたいなブルースをベースにしてるんじゃなく、どちらかというとカントリーとフォークがベースになってるように思う。
私にはけっこう泥臭いサウンドに聴こえるが、彼らの初期のアルバムに比べると「モダンで都会的」だそうだ。
このアルバムで気に入った曲は1曲目「禁断の木の実」、3曲目「オフェリア」、4曲目「アケイディアの流木」、8曲目「おんぼろ人生」です。
心地よいサウンド、ゆったり流れる時間、大人のロックって感じ。
楽しみながら演奏してる情景が浮かんできそうである。
彼らは実力派中の実力派なので、これくらいの演奏はお手の物で、実に余裕たっぷりだ。
中でも「オフェリア」の楽しそうだが哀愁あるメロディがすごく気に入った。
また、ギター・ソロが実に素晴らしい。
リズミカルで、副音を主体にしたカッティングのようなギター・ソロ。
センスがいいし、なんといっても上手い。
他の曲にも言えることだが、所々でセンスの良さを感じさせるサウンドは、やはりベテラン・バンドの風格みたいなのを感じるのだった。
| 名盤100選へ戻る |
カレンダー
| 06 | 2025/07 | 08 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新CM
[02/26 take surveys for money]
[02/03 Ahapenij]
[12/18 Blealgagors]
[12/17 BisiomoLofs]
[12/16 Looporwaply]
最新記事
(07/20)
(10/21)
(10/20)
(10/14)
(10/13)
最新TB
プロフィール
HN:
にゅーめん
性別:
男性
趣味:
音楽 読書
自己紹介:
音楽を愛する中年男の叫び
ブログ内検索
忍者アナライズ
